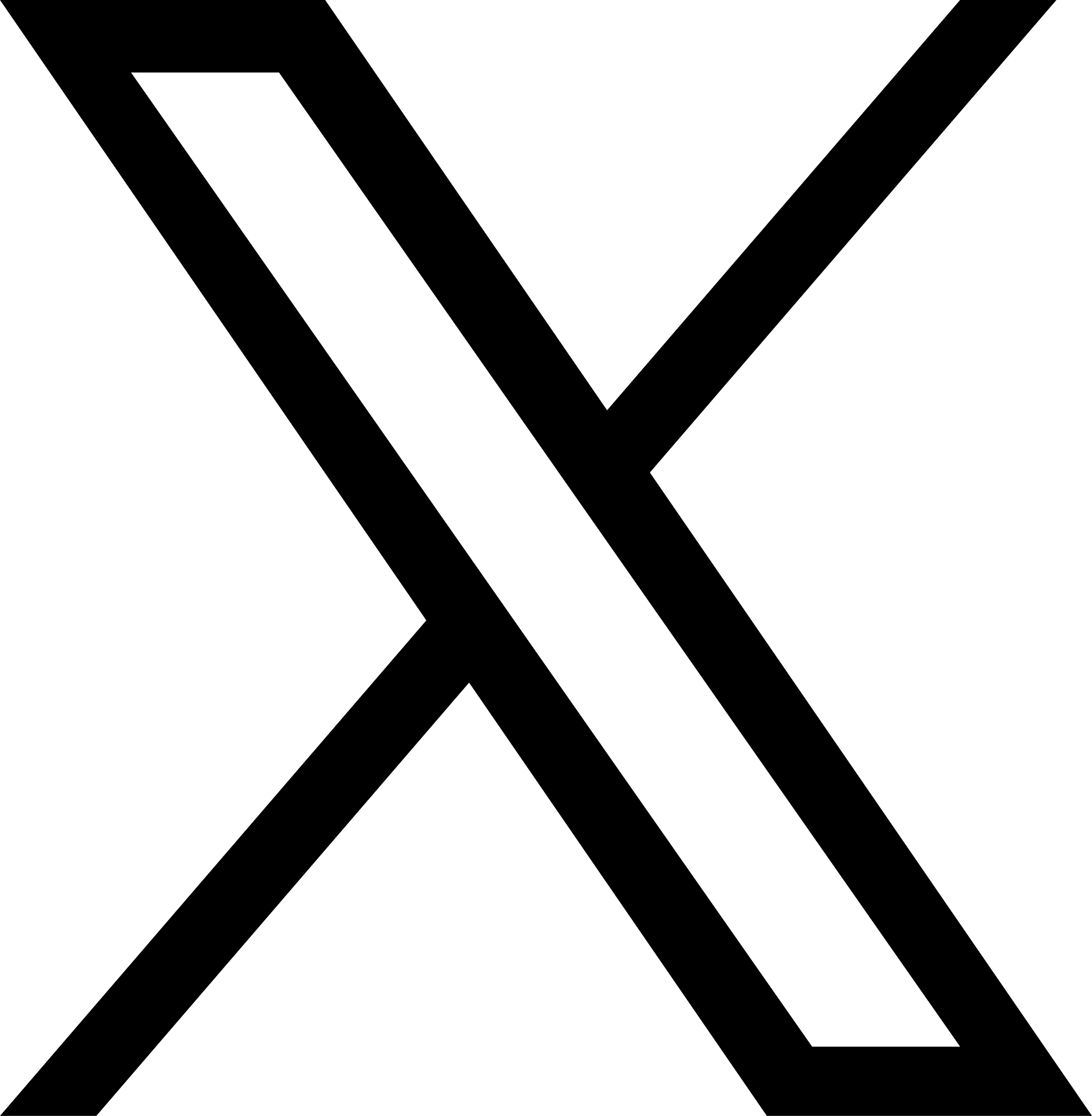第七回 : 遠山 敦子様
2008年03月19日 (水)

遠山 敦子(とおやま・あつこ)
新国立劇場運営財団 理事長
元・文部科学大臣
三重県生まれ。中学校以降静岡県。静岡県立静岡高等学校から、東京大学文科一類へ入学し、法学部へ進学。卒業後は、文部省(現・文部科学省)に初の女性上級職として入省する。初等中等教育局中学校教育課長、高等教育局長などを経て、1994年7月、文化庁長官に就任。文部省を退官後、駐トルコ共和国特命全権大使、国立西洋美術館館長、国立美術館理事長などを歴任し、2001年4月(~2003年9月)、初の民間からの文部科学大臣として小泉内閣に入閣した。2005年4月、新国立劇場運営財団理事長に就任。また、現在は、財団法人松下教育研究財団理事長、独立行政法人科学技術振興機構顧問など、教育、文化、科学の各分野に携わっている。主な著作に、『こう変わる学校 こう変わる大学』(講談社)、『トルコ 世紀のはざまで』(日本放送出版協会)などがある。
寄付者紹介
- 東大法学部卒業後、初の女性キャリア職として文部省(現・文部科学省)へ入省した遠山敦子氏。文部省退官後も、駐トルコ共和国特命全権大使、小泉内閣(第一次)で文部科学大臣を務めるなど活躍された。今回は、東京大学基金へご寄付をいただいている遠山氏に、学生時代の思い出や、これからの東大への期待をうかがった。
世の中に役立てる自分をつくるため、
静岡高校から東大文科一類へ進学
私は、小さな頃から両親に、「これからは女性もきちんと職業に就く時代になる。世の中に役立つような生き方をしなさい」と言われながら育てられたのです。だから、雄大な富士山を眺めながら、将来どうすればいいのかいつも考えていましたよ。静岡高校から東大進学を目指したのは、やはりチャレンジのし甲斐があるということと、当時は女性が仕事に就くことは極めて困難な時代でしたから、東大に進めば何らかの展望が開けそうだという思いもありました。
入学した文科一類は約800人の同期生がいましたが、女性はなんと私ひとりだけ。今では誰も信じてくれませんけれど、学生時代の私はかなりシャイでしたからその状況にはさすがに困ってしまいました(笑)。でも、あの頃の駒場は田園風のキャンパスで、ゆったりとして気持ち良かったですね。哲学、歴史、自然科学、語学も英語、フランス語、ドイツ語を履修するなど、とても充実した教養課程をすごすことができました。
当時は港区の白金に東大の女子寮がありましてね。私もそこに入寮して、大学に通っていたのです。違った学年や、他学部の女性たちとひとつ屋根の下で生活をともにした経験は非常に得がたいものとなりました。今でも女子寮で出会った仲間たちとは交流を持っていますから。ちなみに勉強以外の趣味としては、美術館や庭園巡り、昔から好きだったクラシック音楽と読書くらいでしょうか。世の中に存在している、より良いもの、美しいものを追求しようとしていたのだと思います。
そして教養課程を終え、専門課程に進む際、法学部と経済学部を選択できましたが、私は法学部へ進むことに決めました。自分を世のために役立たせるためには、汎用性の高い法律のコースを学んだほうが良いだろうと考えたのです。
昭和37年、東大法学部卒業後、
文部省初のキャリア職員に
その頃、日本の法律研究の世界では昔ながらの大家であった先生方に代わって、新進気鋭の法学者がどんどん世に出始めていました。憲法では、宮沢俊義先生から小林直樹先生へ。民法では、我妻榮先生から川島武宣先生へ。刑法でも、団藤重光先生から平野龍一先生へ。少壮の先生方が、新たな角度から導き出した自己の論を発信していくその勢いや姿勢から、学問を追求し続けることの大切さを教えていただきました。また、民事訴訟法の三ヶ月章先生が、教室の壇上で新訴訟物理論を颯爽と講義されていたことも覚えています。
一方、法律を学ぶ学生の私でしたが、大教室で行われる授業にはあまり身が入らず。それよりも、法律相談所というサークル活動に一所懸命に取り組みました。これはいわばボランティア的な活動で、一般市民の方々から法律に関する質問を受け、それらの問題にどうやって対処していけばいいかといった相談に乗るというもの。ある意味難解なものとして受け取られがちな法律を、実社会で使える手段として理解してもらうための活動でした。優秀な先輩方とも出会えましたし、この活動は私にとって非常に有意義なものでした。今でもこの相談所は東大の後輩たちが続けているんですよ。
大学卒業後は、どのような道に進もうか考えました。ある民間企業の面接に参加してみたこともあります。その際、「当社は女性の重役は要りません」ととり合ってくれませんでした。そんなことは考えてもいなかったので、大いに驚きました(笑)。昭和37年当時は総合職として女性を受け入れてくれる民間企業は皆無でしたから。そこで、女性の働きをきちんと評価してくれ、また、ポジションも男女差のない公務員になろうと。国家公務員試験I種に合格し、さて、どの省を選ぶか。当時の労働省、厚生省、外務省にはすでに上級職の優秀な女性が入省しておられました。でも私は、どうせなら初めての道を切り開いていくほうが面白いと思ったのです。そして、初の女性上級職として文部省に入省することになりました。
駐トルコ共和国特命全権大使、
文部科学大臣として小泉内閣への入閣
文部省に入省してからは、当然ですが、係長になったのも、課長昇進も、局長、文化庁長官就任も、女性としては常に「初」。でも、私は性別に関係なくひとりの人間として全力で与えられた仕事をこなしてきただけです。上司の方々も温かく私に接してくれましたし、どんどんポストと仕事を与えてくれました。公務員の仕事は、決められたミッションを全うすること。与えられた仕事がいくら難しくても、逃げないで正面から取り組む。そして一所懸命ひとつの仕事をクリアすれば、次にはさらに難しいミッションが与えられる。その繰り返しで成長していくことができます。
いくつもの思い出深い仕事に携わりましたが、昭和50年代前半には膨大な学術情報をデータベース化し、ネットワークで大学間をつなぐ学術情報システムの構築、文化庁では600億円に上る芸術文化振興基金の立ち上げ、現在、理事長を務めている新国立劇場は、日本で初めて空中権という概念を用い国費ゼロで竣工にこぎつけました。本当に前例のないことばかり(笑)、不可能を可能にするという使命を自分自身に課し続けた40年の霞ヶ関生活だったと思います。前例中心主義の官僚の世界では異例なことばかりやってきました。ラッキーなことにいくつもの結果が残せたのは、同僚や上司はもちろん、様々な分野で活躍している外側のたくさんの応援団がいてくれたからこそ。いくら感謝しても足りません。
文部省を退官後は、晴天の霹靂ともいえる、駐トルコ共和国特命全権大使の任命、その後、さらなる晴天の霹靂である、文部科学大臣として小泉内閣への入閣。本当はそろそろゆっくりしたいと思っていましたが、私にはNOと言える勇気がないんですね(笑)。自分にとってそれが必然だと思えば、たとえ難しくても愚かにもいばらの道に進んでしまう。でも、与えられたポジションでは命がけで最善を尽くす。お受けした以上は、そうすることが当然だと思ってやって参りました。国立大学の法人化という世紀の大改革も実現できました。そうそう、学生時代にある本でこんな話を読んだのです。「林に入って、広い道と狭い道が先に続く分かれ道があったら、狭い道を選んだほうが面白い」と、確かそんな内容でした。思えばその時以来、私はずっと困難の道を選びながら人生を歩んでいるのでしょうね(笑)。
東大で学んだ人間としての信頼感。
その価値を与えられた感謝に代えて
様々な方々から期待していただき、仕事を任せていただけたのは、東大で学んだ人間である私への信頼感もあったのだと考えています。その感謝の意味もあって、寄付をさせていただきました。21世紀は「知の世紀」です。人しか資源のない孤立した島国日本が、国際競争がさらに激化する未来を生き抜いていくためには、優秀な人材を育成するしかありません。それにはもっともっと大学が良くならないと。その事実をしっかり自覚して、深い教養と先端研究に意欲を持った学生をどんどん輩出していただきたいですね。
本当にいい大学かどうかを計る場合、世界のトップクラスの研究者や優秀な学生がいつも集まっているかどうかを見ます。でも東大は、もっと上を目指せるはず。まずは中にいる先生や学生が視点を、国内外の大学など、できるだけ外に向けることが大事です。異なるカルチャーのぶつかり合いが新しい価値を生み出します。特に学生には短期間でもいいので国外で学ぶ経験を積んでほしいです。また、日本はいまだに男性優位の社会であることは否めません。ハーバードやMIT、ケンブリッジなどは女性の総長が出ていますし、トルコの大学でも女性のプロフェッサー比率は3分の1を超えていました。チャンスさえあれば、女性は責任をもって結果を残します。逃げないんですよ、私の経験からしても(笑)。ですから、もっともっと女性の可能性を活用するべきだと思っています。
東大の学生は、とても恵まれた環境で学ぶことができています。まず人生の志や目的を明確にして、才能、能力を高めて使うべき。自分のためだけではなく社会のために自分を生かすことができれば、その人の人生は必ず倍の楽しさになりますから。“ノブレス・オブリージュ”と同じように、東大の学生にはその義務があるのです。困難に立ち向かい、学び続けながら、ぜひ、手ごたえのある生き方をしていってほしいですね。
取材・文:菊池 徳行
※寄付者の肩書きはインタビュー当時のものです。