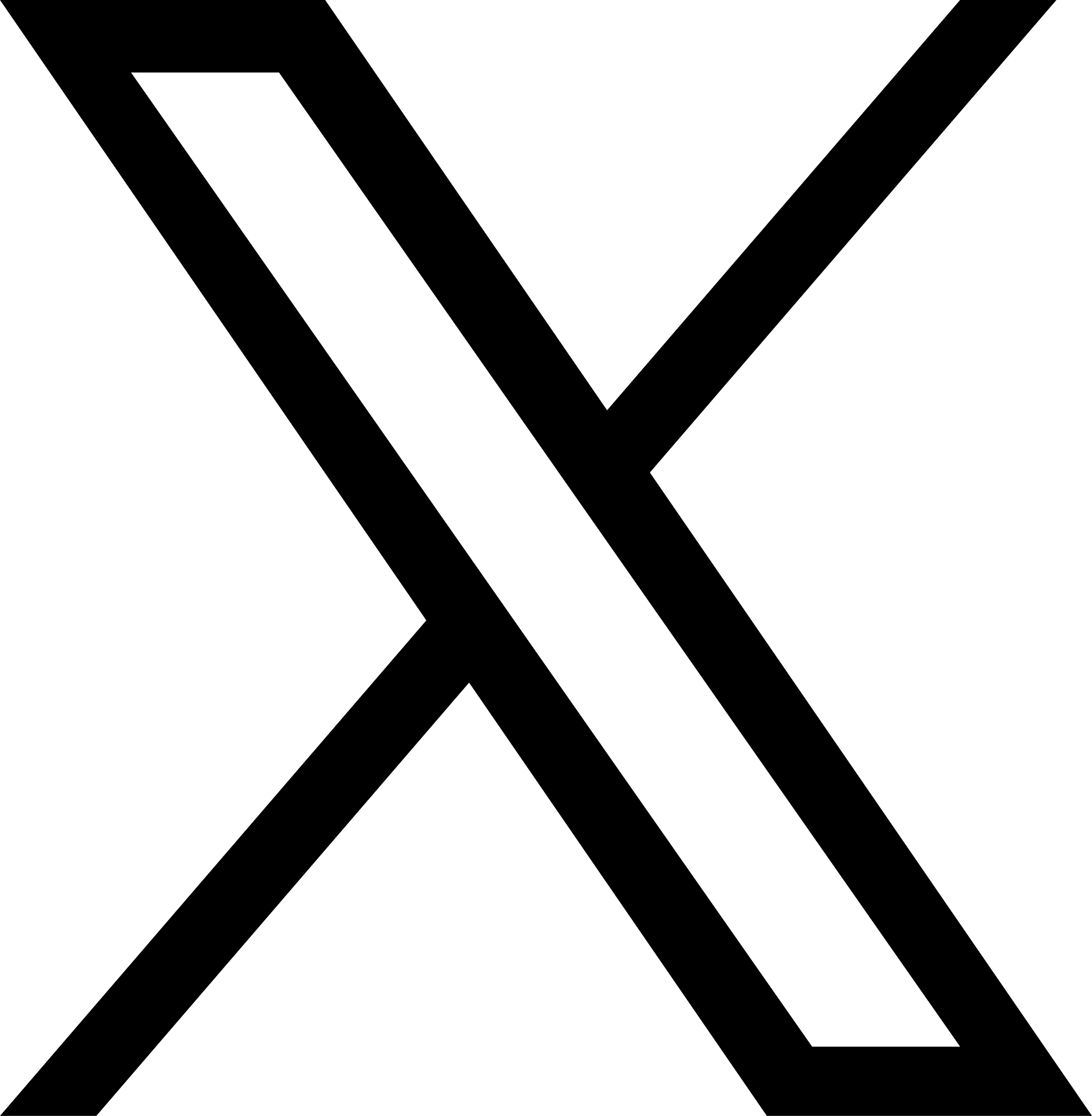「東大のおかげでいまの私があるから」
新進フィルムメーカーの母校への恩返し<第27回>
2024年11月19日(火)

後藤 美波(ごとう・みなみ)様
1993年静岡県生まれ。東京大学文学部(美術史学専修)を卒業し、米コロンビア大学大学院フィルムスクール修了。日米で数々の短編映画を執筆・監督・プロデュースした経験を持つ。脚本・プロデュースを務めた長編映画「ブルーイマジン」はロッテルダム国際映画祭で世界初上映され、大阪アジアン映画祭、ホーチミン国際映画祭などで受賞し、国内で2024年3月に封切りされた。
母校である東京大学に、本当に感謝しています。在学中に経験した体験活動プログラムや、情報学環教育部、FUTI(東大友の会)の奨学金を活用させていただいてのコロンビア大学大学院フィルムスクールへの留学など、多角的な活動に参加できたおかげで、いまのフィルムメーカーとしてのキャリアを歩み始めることができたからです。
また、大学時代のつながりはかけがえのないもので、いまでも友人とは連絡を取り、定期的に会って励まし合っています。卒業生はみなそうではないかと思うのですが、大学の名前で信頼してもらえたり、興味を持ってもらえたりすることもあります。
この「寄付者インタビュー」に登場されている他の方々のように大きな貢献はできておりませんが、少しでも母校に恩返しをしたいと思って、自分なりにできる範囲からではありますが、寄付をしています。

「ドラゴン桜」がきっかけで東大受験へ。
美術史を学びたくて文学部に進む。
はじめて東京大学という存在を意識したのは、父の影響でした。当時は「ドラゴン桜」が流行していて、父がどハマりし、娘を東大に送り込むぞ! と燃えてしまったようです。それで、漫画やドラマも見せられましたし、塾の東大進学コースなどにも入れてもらいました。それだけ期待をかけられ、勉強しているうちに、私自身にも東大を受験しようという気持ちが芽生えてきました。
私は浜松の出身です。受験勉強は決して楽ではありませんでしたが、たのしみなこともありました。塾の夏期講習などの特別授業の際、大阪や東京に行ける機会があったのです。それで、はじめて梅田の広大な駅を歩き回ったり、はじめて渋谷のスクランブル交差点を横断したりして、大都市の活力に触れながら「東京に住めたら楽しそう」などと具体的な想像を膨らませることができました。それまでずっと浜松に暮らしていたので、勉強を口実にいろいろな場所へ行くことができて、それがモチベーションにつながっていました。
文科三類を選んだのは、もともと美術館が好きだったからです。美術を学べる文学部が自分に合うかなあと思って。
専門分野を選択する際にはそのとおり、文学部の美術史学専修に進みました。いま私はフィルムメーカーとして活動していますが、はじめから映画の道を選ぼうとは考えていませんでした。映画を観るのは好きだったので、渋谷のアートシアターなどに足を運んで楽しんではいました。でも、自分が作る側に行くことはないだろうと思い込んでいたので、映画系のサークルなどにも入らずにいました。むしろファインアートが好きで、夏休みはバックパックでアメリカやヨーロッパを旅して、1日に何軒もの美術館を巡って歩くような学生でした。将来の職業としては、学芸員がいいかなと考えていました。
海外への関心は大学に入学したころから強くて、アドミニストレーション棟に足を運び、海外関係のワークショップをチェックしていたような気がします。そこで見つけたのが、「体験学習プログラム」でした。
体験学習プログラムで米国の大学院を知り、
情報学環でストリップ劇場の映像を作る。
私が参加したのは、ロサンゼルスで映画学校の見学や現地の人にインタビューなどをして、自分たちで簡単な映像を作るプログラムです。大学3年生のころでした。現地では、東大出身でアメリカの大学院フィルムスクールに通っている方とお話しする機会もありました。それまでは、芸術系の学部にいっていないと、芸術系の大学院には進めない、という固定観念がありました。でも、アメリカではバックグラウンドを問わず、大学院から芸術を学べることもあると知れたのです。美術が好きで学芸員資格を取得中でしたが、NetflixやHuluなどの映像配信メディアが急成長して日本でも広がっていたころで、私の考えにも変化が生じていました。浜松には美術館が少なかったこともあり、垣根が低くも新しい世界を見せてくれる芸術は映像ではないか、と思うようになってきたのです。東京で暮らすうちに、地元に届けられる芸術に携わりたい、という気持ちがわいていました。この体験プログラムでの経験から、自分の進路としてアメリカのフィルムスクールが明確に浮かび上がっていたように思います。

大学生活で最も思い出に残っているのが、情報学環教育部での活動です。社会人や他の大学からの学生も多くて、多様な人に出会うことができたし、コロンビア大学院フィルムスクールに提出することになるポートフォリオの原型となった作品を作る機会も得られました。
その作品は、上野の不忍池の近くにあるストリップ劇場を舞台にしたドキュメンタリーです。二人組で作ったのですが、その子と半年くらい劇場に通い詰めて撮影しました。通っているうちに顔を覚えてくれ、常連さんたちも徐々にお話ししてくれるようになって。とても優しい劇場でした。ダンサーさんや、仲良くなったお客さんを撮影させていただき、10分くらいに編集してまとめました。機材や編集ソフトの使い方に詳しくなかったので、とりあえずやってみようという、いまにして思えば雑なやり方で(笑)。試行錯誤しながらの製作でした。外には出さないという約束で撮影をしていたので、一般公開はできないのですが、私の映像製作の原体験になっています。
ストリップ劇場を収めた短編ドキュメンタリーには英語字幕をつける必要があったので、文字数やタイミングなど自分なりに字幕のルールを学んでつけました。まわりにアメリカ留学をする人もおらず、体験活動プログラムでお会いした先輩に連絡してみるなど、出願の正攻法もわからないまま自分なりに考えて動かないといけなかったので、とても不安でした。そのなかで、林香里先生(現東京大学理事・副学長)は「がんばってね」とよく励ましてくれ、推薦状も書いてくださいました。そのように応援してくださる方の声が、本当に励みになっていました。
そこまでしてコロンビア大に進もうとしていたのは、一度はアメリカに留学したいという強い思いがあったからです。アメリカには何度もバックパッキングで旅していて、特にニューヨークは芸術にあふれた美しい街だと感じていました。ニューヨークには有名な映画学校が複数あり、コロンビア大の大学院に合格することができました。コロンビアのフィルムスクールは、監督・プロデュース・脚本のすべてを1から学べる場所だったので、結果的に良い選択だったと思っています。
パーティの残りものを食べた留学時代、
奨学金で得た心理的安定が原動力に。
私は3年間のプログラムで留学したのですが、1年目は奨学金をもらわずに行きました。というのも、卒論などと重なって、アメリカの大学院への応募がぎりぎりになってしまったので……。多くの奨学金は、留学先の合否が出る前から選考プロセスが始まるので、間に合わなくて。だから、はじめの1年は親にだいぶ無理をさせてしまいましたし、ニューヨークの生活費は高いし映像課題の制作費もかかるしで、今思えば大変な時期でした。学校のパーティで残った料理を大量にもらって、それを寮の冷蔵庫につめこんで、数日に分けて食べたことが何度もありました。
2年目は経済的な心配なく学校生活に打ち込みたいと思い、色々と調べて、FUTI(東大友の会)に留学生向けの奨学金があることを知りました。自己推薦書を書くのですが、なんとしても奨学金を獲得したかったので、自分の情熱を思い切りぶつけました。つい先日、FUTIのイベントでオンライン公演をさせていただいた際、選考委員の方が私についてお話をしてくださったのですが「すごくパッションがあったので覚えています」とのことでした。よほど暑苦しい内容だったのだろうと思います(笑)。

FUTIの奨学金をいただけたのは、本当にありがたいことでした。それでも学費とニューヨークの生活費というのは非常に高くて、他の奨学金を組み合わせ、学内のアルバイトをしてなんとかやっていた、というのが現実です。でも、おかげで2年目からは心理的な不安が少なくなったので、1年目よりも勉強に打ち込んで生活することができました。
フィルムスクールで学んだことは、すべて自分の基礎になっています。アメリカの大学院には世界中から学生が集まります。私のころは24カ国くらいから集まっていたと記憶しています。そうなると、国によって映画の作り方、考え方、資金調達の仕方が全然違うことが自然とわかります。「これが正解」ということが存在しないのを最初に知ることができました。
例えば、資金調達でいえば、ヨーロッパではグラント(助成金)ありきで製作することが多く、日本では製作委員会をつくって、興業で取り返そうという意識が強い気がします。アメリカでは寄付してくれる人がいたり、投資してくれる銀行やファンドがあったりするので、自分に合う機関などをどうやって探すか? という考え方になる、など。このように、立ち上げの時点から考え方が変わってくるのです。
フィルムスクールには、修了してデビュー作を発表した人を招いたマスタークラスがよくありました。自分より一歩二歩先に進んでいる人のリアルな話を聞けるわけです。それも、いろいろな国から来てくれます。私のころには、アメリカだけでなく、韓国・中国・イギリスなどのフィルムメーカーから話を聞けました。机上の話ではなく、映画製作にまつわる具体的かつ現実的なステップを教えてくれるので、映画作りを進める上でとても参考になりました。

修了後のフィルムメーカーとしての活動。
最新作「ブルーイマジン」に込めた願い。
コロンビア大学大学院を修了してからは、ニューヨークで映像会社や配給会社の複数のインターン経験をした後、帰国しました。そのあとは、映像と関係ない一般企業に就職したこともあったのですが、一貫して映像作品を作り続けてきました。ドキュメンタリーを製作している間は会社にカメラと三脚を持っていき、終業後にインタビューに出かけることもありました。
そのドキュメンタリーが「SHADOW PIECE」です。女性が作品を作り続ける上でたくさんの障壁があるということを、塩見允枝子(みえこ)さんというアーティストを軸にして描きました。過去も現代も、美術学校に進む女性は多いのですが、美術館に展示されるような作品や、美大の先生に選ばれるのは明らかに男性が多い。社会の構造や結婚・妊娠といったライフイベントなど、女性が作品を作り続けるには様々なハードルが存在するということを、私自身も社会に出て強く実感しています。塩見さんと自分自身を重ね合わせるスタイルで、約10分間の映像にまとめました。

最新作は、今年3月に公開となった映画「ブルーイマジン」です。私は脚本を執筆しました。現代の東京・巣鴨を舞台に、女性たちの信念と連帯と葛藤を描いた、青春群像劇です。さまざまな形の性暴力、DV、ハラスメントに悩まされる人々に寄り添うシェアハウス「ブルーイマジン」に集まった女性たちが、勇気をふりしぼって連帯し、自分と世界を変えるために声をあげようと葛藤する物語です。
脚本執筆のためのリサーチで、たくさんの性被害についての体験記を読み込みました。そういう悪夢を見る日があったほどに。でも、ハラスメントや性暴力はこの世に現実としてあるものです。世の中の意識が良い方向に変わっていくといいな、という願いを込めて書きました。
母校・東大に寄付する2つの理由。
女子学生支援で安田講堂の銘板掲載へ。
私が母校の東大に寄付する理由は2つあります。1つは、アメリカで当然のように寄付をする文化に触れ、素敵だなと感じたこと。さらに、たくさんの方々の寄付により、私がいただいたFUTIの奨学金が成り立っていると知ったことです。
アメリカではカジュアルに寄付が行われています。たとえば、音楽会に当日行けなかった場合、そのチケット代をすぐ寄付に回すことができる。そしてリクエストすれば税の控除を受けられることも。人々のモチベーションを上げる仕組み作りもうまいのですね。そのように自然に寄付ができるのって、とてもいいことだと感じていました。
もう1つは、私の父が本郷キャンパスの図書館改装の際に寄付をしていたということ。父は東大出身ではないのですが、寄付というかたちで東大に関われたのがすごく嬉しいと喜んでいて。それを見ていたら、なんかいいなあと思ったんですね。
その時に「(お金持ちでもないのに)よく寄付するね」と父に言ってしまったのですが(笑)、「いやいや、一部は税控除で返ってくるんだよ」と教えてくれて。それではじめて、東大への寄付でも税控除の対象になるんだ! と私は知りました。

私は主に「さつき会奨学金基金」に寄付をしています。卒業してから数年経っても、女子学生が約20%という男女比が変わっていなかったことを知ってショックを受けました。特に、私がいた大学院のクラスは男女が半々だったので、翻って東大の男女比を見ると異様に感じました。あらためて問題意識を持って調べてみたら、学力や興味があっても、周りの大人たちから様々なジェンダーバイアスをかけられて東大を選択肢に入れない(入れられない)女性が多いことを知りました。
その後、さつき会は自宅以外から通学する女子学生を対象に奨学金を出している、と読んだのが、寄付を始めた直接のきっかけです。私も地方出身だからわかるのですが、「都会は危ない」「しっかりした賃貸や寮じゃないと、娘を東京の大学には行かせたくない」と思っている親御さんはけっこう多いと思うのです。そういう場合、お金に余裕がなければ東大は進路の候補から外れてしまいますよね。来たいと思っているのに経済的な理由で東大進学を諦めてしまう女性がひとりでも減ったらいいと願い、寄付しています。
最近、東大でも女性の意欲を削ぎ、未来の可能性にまで影響を与える恐れのあるこうした言葉を可視化する「#言葉の逆風」プロジェクトを行っていましたよね。私もかつて「女の子なんだから、地元の大学でいいでしょ」とか、「女の子は浪人するとみっともない」とか言われたことを思い出しました。でも、大学を挙げてそのようなプロジェクトに力を入れていることを知り、さらに応援したい気持ちが強まりました。
寄付の結果、安田講堂に永久に銘板を載せることができることになり、すごく嬉しかったです。自分にとって大切な大学生活を過ごした思い出のあるキャンパスだし、歴史ある建築ですしね。そんな立派な建物に本当に自分の銘板を載せてもらっていいのかな? という気持ちにもなりました(笑)。でもやっぱり、実際に銘板を見た時には、こういう形でずっと大学と関わりを持ち続けられるのって素敵だな、と感じましたね。
取材・文・写真:東京大学基金事務局