理学部情報科学科で育まれた学びと仲間
ー次世代へのエールを寄付に込めて<第28回>
2025年05月21日(水)

小西 祐介(こにし・ゆうすけ)様
2007年、理学部卒。2009年、情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修了。同年、Google日本法人に入社。Google Play、Android、Googleショッピング等のエンジニアリング、製品開発を担当。2014年にファイブ株式会社を共同設立。現在はエンジェル投資・技術顧問・子育ての傍ら、ソフトウェアエンジニアリング協会にてコンピュータ科学の普及活動を行っている。
理学部情報科学科の学生が学ぶ理学部7号館の大規模修繕のために「コンピュータサイエンス教育支援基金」が設置されました。同学科卒業生で本基金にご寄付いただいた小西さんに、東大の在学生であり、東大基金でファンドレイジングサポーターとして活動している私、ゆめが、寄付に込めた想いや理学部での思い出についてインタビューしました。
これまでのキャリアと理学部情報科学科での学びについて
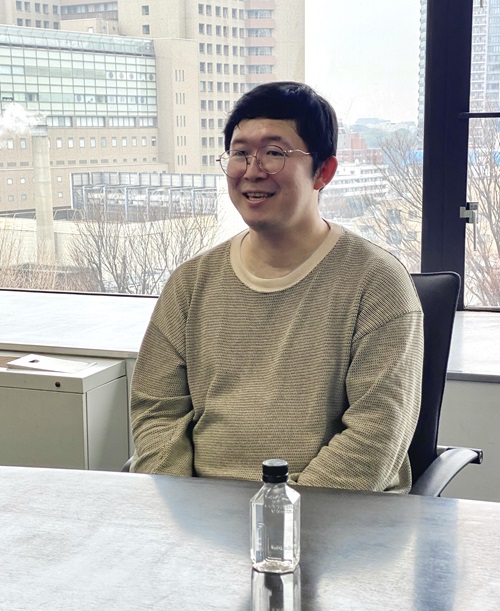
Q:理学部情報科学科を卒業されてからのキャリアについて教えていただけますか?
A:2009年に大学院を修了して、新卒でグーグル株式会社に入社しました。様々な部門を経験したあと、スタートアップで頑張ってみたいと思い、2014年にスマートフォンの動画広告の事業を行う会社を設立しました。事業は順調に成長して2017年にLINE株式会社に買収されました。その後、スタートアップのエンジェル投資や技術顧問を行いつつ、友人とソフトウェアエンジニアリング協会という団体を立ち上げました。現在はエンジニアの成長支援や教育活動に取り組んでいます。
Q:理学部で学んだことがお仕事に活きていると感じることはありますか?
A:もう何から何まで、って感じですね。コンピュータがどう動いてるのかという基礎から、実践的なスキルまで、全部ここで学びました。特に印象に残っているのが、7号館の「地下室」です。ここで友達と課題について一緒に考えたり、バグに悩んだりと、みんなで学び合う場でした。
Q:地下室って、多くの卒業生が思い出の場所だと語ってくださる場所なんですよね。
A:ほんとに懐かしいですし、楽しくて幸せな時代でした。理学部情報科学科って、授業はそんなに多くなく、演習に大半の時間を使うことになる。課題がたくさん出るんですけど、説明はほんの数分だけで「再来週までに頑張って作ってきてね」みたいな感じで(笑)。地下室で友達と教え合いながら、切磋琢磨してました。課題もやろうと思えばどこまでもこだわれるのでとことんやりたくなっちゃって。
Q:難しい課題に燃える人たちが多かったんですね(笑)
A:そうですね。オセロのAIを作ろうとか、CPUを作ろうとか。。地下室に泊まることもありました。家に帰るのも面倒くせえみたいな感じで、気絶する寸前までプログラム書いて、疲れたら地下室の椅子を並べて寝る、みたいな。。。念のため言っておきますと、そういう生活をしていたのはごく一部の人間だけで、あまりおすすめはしません(笑)。
地下室は友達と一緒に仲良く、教え合いながら課題をこなしていく場所でした。プログラムやコンピュータ好きなメンバーなので、自分がやったことを「すげーだろ!」と見せ合いながら、刺激を与え合いながらやっていました。
Q:ともに過ごす時間も長いですし、学科の人たちとはすごく仲が良かったんですね。
A:今でも一緒にお酒を飲んだりしますね。大学時代の人間関係は、今の自分にとっても大事な財産です。同窓会もホームカミングデーの日あたりで毎年開かれています。
今回の寄付のことは同窓会で知りました。「7号館を新しく大規模修繕するけど、お金が足りないから寄付してくれる人がいると嬉しい」と紹介していただきました。
寄付についての想い

Q:どういう思いでご寄付されたのでしょうか?
3〜4年生、修士の期間を通じて、情報科学科にはすごく育ててもらったと思っています。好奇心の赴くまま好きなことに没頭でき、友人もたくさんできた、かけがえの無い場所です。ただ、建物は老朽化が目立つなど、当時から環境面には課題があった。もっと健康的で快適な場所になればいいなという気持ちで寄付しました。
もともと、ITスタートアップの売却でできたお金なので、スタートアップやエンジニアのコミュニティにお返ししたいと考えていたんです。私は自分のためにお金を使うのがあまり得意ではなくて。「お金を自分のために有効に使うのには限度があるけれど、他の人のためならいくらでも良い使い道がある」と思っています。
Q:お金を社会のために使う、という意識を強く持たれているんですね。
そうですね。世の中には夜の街で散財するような使い方もありますが、私はそれよりも、東大の学生がもっと活躍できるようなことに使いたい。お金が社会を良くする方向に使えれば、それが一番嬉しいです。
今後の展望
Q:これからはどういった活動をしていきたいとお考えですか?
今はソフトウェアエンジニアリング協会で友人たちとエンジニア教育活動をやっています。「天才だけがエンジニアになれる」わけではない。やり方さえ分かれば、誰でもなれると信じているので、それを証明していきたいです。
それから自分でまたスタートアップを立ち上げたいという気持ちもあります。いずれは協会の活動で育ったエンジニアたちがいろんなところで活躍し、自分の事業にも関わってくれると面白いですね。
コンピューターサイエンス分野や後輩の学生に期待すること
Q:これからのコンピューターサイエンス分野に期待することはありますか?
社会に大きなインパクトを与えるような技術、たとえば今は生成AIみたいな大規模言語モデルのようなものできてきていますが、まだ見ぬ技術も生まれてくると思います。
そうした技術を単に研究室の中で終わらせるのではなく、社会の中でどう活用するか、という観点も含めて研究・教育を進めていってほしいです。
Q:東大生や情報科学科の後輩に対して、どんな期待をお持ちですか?
情報科学科の卒業生から、大きくても、小さくても、「私がこれをやりました!」と言えるような研究やプログラムが生まれるのを期待しています。そして作ったものを、より多くの人に届けることにぜひ挑戦してみてください。みんなが作ったものが、みんなが使える形で積み重ねることで、社会が少しずつ良くなっていくのだと思います。また、ソフトウェアエンジニアの起業は、他の業界と比べて初期コストが低く、資金調達しなくても、自分の時間だけで試してみることができる。うまくいかなくてもその経験自体は必ず財産になる。だからぜひみんな挑戦してみてほしいですね。そして、将来うまくいったら、周りの人や未来の世代に還元してあげて欲しいです。
学生へのメッセージ
Q:最後に学生、特に情報科学科の学生に向けて、何かメッセージはありますか?
情報科学科では、真面目に勉強していれば、世界最先端で戦えるだけの知識が身に付きますし、ゼミや課題のやり取りなどを通じて自然とたくさんの友人ができます。
何かに挑戦することを恐れず、大胆にサイコロを振ってみてください。王道の進路だけが全てではありません。他の人と違う「獣道」みたいな進路でも、意外とうまくいくこともある。命綱をしっかりつけた上で、リスクを過大評価せず、挑戦してみてほしいです。
難しい挑戦でも、真剣に取り組んでいれば周りの人は見てくれていて、助けてくれるはずです。
社会人や寄付者へのメッセージ
Q:社会人の方々や、寄付された・される方々に向けては?
まずは自分自身が幸せになるためにお金を使って、その上で、家族や友人など身近な人たちのためにお金を使って、さらに余裕があるなら、みんなで社会をよくするために使っていく。そういうお金の使い方は有意義だと思いますし、そんな風にお金を使う人が増えていくと、もっと良い社会になると思います。

インタビューを通して
小西さんに理学部での思い出をたくさん伺い、理学部7号館でとても素敵な時間を過ごされ、母校への恩返しの気持ちや後輩たちへの期待も込めてご寄付いただいたのだなと思いました。
また、「挑戦することを恐れず大胆にサイコロを振ってみてください。真剣に取り組んでいれば周囲も助けてくれるはずです。」という言葉が非常に印象に残りました。私は修士一年ですが、あと2年の学生生活でも失敗を恐れず、もっともっと新しいことにチャレンジしていきたいと思います。



