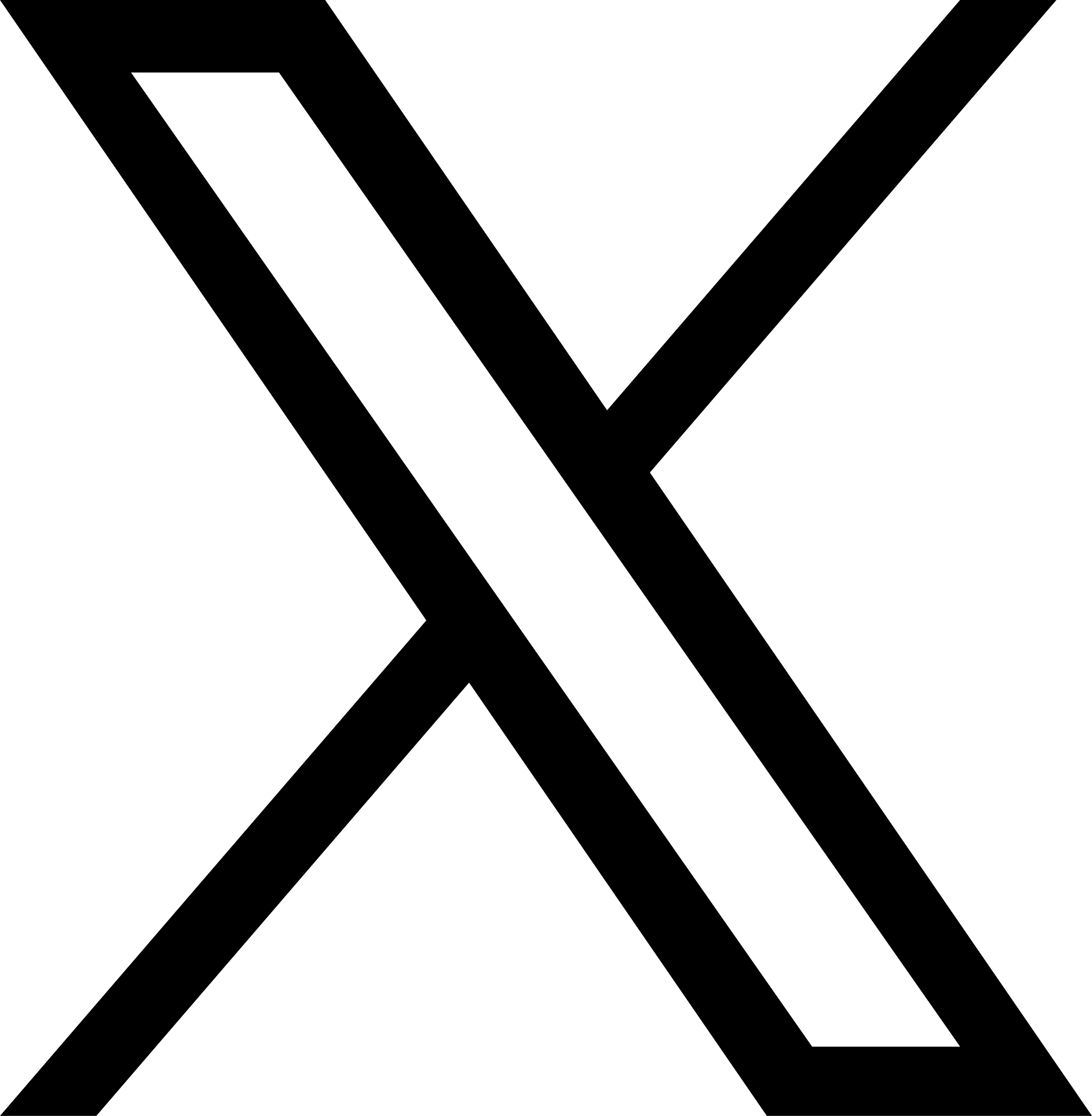みなさん初めまして、学生ファンドレイジングサポーターのそらです。
東大駒場リサーチキャンパス公開の前夜、駒Ⅱ音楽祭第5回公演”響創”が行われ、“Ensemble Eve”と銘打たれた一流の演奏者たちが、この夜のために特別に集結しました。静謐な夜の空気の中、格調高くも温かみのある音楽が満ち、まさに「前夜祭」にふさわしい特別な空間が生まれていました。
まず、主催者の戸矢理衣奈先生に音楽祭に対して込めた想いをインタビューし、熱意を存分に受け取った上で音楽祭の様子をレポートします。
戸矢先生インタビュー:明るさの基盤にある横のつながり
まず、音楽祭の概要を教えていただけますか?
駒Ⅱ音楽祭は、「科学と芸術は、目指すところは同じである」という考えに基づいています。駒場第二キャンパスにおいて、「科学と芸術が近くにある環境を作りたい」という思いから、この企画を立ち上げました。
背景について少し説明しますと、私は生産技術研究所(生研)にて「文理融合の推進」を担当しています。しかし、いきなり文系と理系の研究室同士が議論を始めるのは難しいので、何らかの“緩衝地帯”が必要になります。芸術、特に音楽は、そうした役割を担う場として非常に有効だと考えました。
実際、この音楽祭が始まる以前から、生研では音楽に注目した活動を続けてきました。たとえば「文化×工学研究会」という研究会では、 各界で活躍されている方をお招きして、潜在的に工学と関係のあるテーマでお話をいただいています。この会では過去に何度も、西洋音楽史をご専門とされる岡田暁生先生(京都大学名誉教授)にご講演をいただきました。その場に東京フィルハーモニー交響楽団のコンサートマスターで、東大先端科学技術研究センター(先端研)で特任教授を務められている近藤薫先生が来られ、同じ駒場第二キャンパスにある両所で、一緒になにかをしようという話になりました。近藤先生もそれまでに先端研でコンサート等の実績を重ねられています。近藤先生や賛同してくださった方々とともに、音楽祭の構想を練り、2024年2月に発足記念公演を行いました。
「文理の緩衝地帯が音楽」というのが非常に興味深いです。それを思いついたきっかけは何だったのでしょうか?
背景にはいろいろな経験があります。私は東大が社会人向けに行っている「Executive Management Program(EMP)」を受講したのですが、そこで出会った医学部の先生が「真理の探究という点では、科学も芸術も本質的には同じである」とおっしゃっていて、その言葉が非常に印象に残りました。ちなみにその先生はかつて本郷でクリスチャン・ツィメルマンという世界的なピアニストを招いたコンサートを開催されています。私自身も強く共感し、それを実践しうる場をつくりたいと思うようになったんです。
実際に、文化が学問や実務に影響を与える事例はありますか?
はい。私はかつて、株式会社資生堂の初代社長・福原信三さんがどのようにして資生堂をブランド化していったのかを研究していました。
福原信三さんは1873年生まれで、主に大正時代から昭和初期に活躍された方ですが、写真家としても高い評価を受けていました。彼には『光と其の諧調』をはじめ、複数の写真をめぐる著書もありますが、自身の写真論を、企業経営にも大いに活かしていました。こうした芸術から得られた着想が経営に反映されている事例から、私自身も非常に大きな影響を受けました。芸術から学ぶことは本当に多いと実感しています。
「駒場らしい音楽祭を目指している」と伺いました。具体的な工夫について教えてください。
たとえば、昨年11月には指揮者の山田和樹さんをお招きし、「やまだこんどう音楽実験室」と題した公演を行いました。指揮者がいる場合といない場合で演奏がどう変わるかなど、音楽に関する“実験”を交えた構成にしました。
また、今年1月の第4回公演では、バルトークとショスタコーヴィチという、東欧と旧ソ連の作曲家の作品を取り上げました。クラシックファンから見ても「渋い」曲目ですが、「楽しいだけが音楽ではない」と掲げて、西洋音楽史の第一人者である京都大学の岡田暁生先生をお招きし、演奏前に30分のご講演をいただきました。旧ソ連や東欧の政治情勢や文化的背景を知った上で音楽を聴くことで、より深く音楽に接してもらえるように工夫しました。


今回はどのようにしてコンセプトを決めたのですか?
私たちが駒Ⅱ音楽祭で一貫して大切にしているのは、単なるコンサートで終わらせないことです。
芸術界とのネットワークが広がる場にしたいという思いがあり、今回近藤先生が自ら声をかけてくださって、現在の日本クラシック界を牽引する15人の方々が集まってくださいました。こうした機会を重ねることで、例えば個人的な交流が生まれることも重要だと思っています。今回のコンサートのコンセプトとしては、近藤先生のお考えで「生と死」がテーマになっています。
教員や学生に加えて、寄付者の方もいらっしゃると聞きました。どのような方が応援してくださっているのですか?
寄付をしてくださる方の多くは、コンサートに足を運んでくださる音楽好きの方々です。
中には、特別に音楽が好きというわけではなく、いわば「東大をもっと文化的な場所にしたい」という思いから応援してくださる方もいます。たとえば、私がEMPでお目にかかった、現代アートの分野で世界的に活躍されている方は、日本の外交官は文化の話ができない、東大は、こういうところを変えていってほしい、という趣旨のお話をされていました。フランスの外交官は話が面白い、自国の文化について、自然に語れることが大切なんだ、ともおっしゃっていました。
東大の中に、文化や芸術に自然に触れられる環境があることが、そうした状況を変える一歩になるものと思います。EMPには実務家が多いという背景もあるのですが、同様の発想から、応援してくださる方もいらっしゃいます。
文化を語れる人が育つかどうかは、何が違いを生むのでしょう?
それは、自分の専門分野に閉じこもらず、他分野にもアンテナを広げられる環境かどうかだと思います。私は1年間スタンフォード大学に訪問研究員として滞在したのですが、あちらではカルチャーとして“横のつながり”が非常に作りやすい環境がありました。「面白い人が来るから、ちょっと来ない?」という感じで、気軽に誘い合う文化がある。まったく違う分野の人と自然に出会えるんです。横の広がりがあることで、チャンスが増えるという感覚もありました。大学で専門性を極めるのも大事ですが、それだけではもったいない。スタンフォードでは、アンテナを広く持っている人が本当に多くて、ベンチャーなどに挑戦しながらも、失敗してもまたやり直せばいいという精神的な明るさが根底にあるように感じました。いろいろな考え方があると思いますが、文化への感受性も、そうしたつながりから生まれるのかもしれません。

音楽祭に込めた思い、「こういうふうに受け取ってほしい」というものがあれば教えてください。
私はよくこの音楽祭を「環境にしたい」と言っていますが、まさにそれです。特別なイベントというよりも、年に何度か気軽に音楽を聴きに来て、リフレッシュしてもらえたらいいなと。
音楽には「嫌なことを忘れさせてくれる力」があるし、物の見方を変えてくれるような体験に繋がることもあると思います。圧倒的な演奏に触れたあとには、日常のものの見方が少し変わることもあるでしょう。そもそも専門分野でなくても、音楽をはじめ一流のものに触れた経験は、後になって何らかの形で花開くことがあると思います。それを大学という場で、特に若い人たちに体験してほしいと考えています。
大学の200人規模のイベントで、これだけのレベルの演奏者が集まる機会はなかなかありません。最前列だと、山田和樹さんのつぶやきが聞こえることもあるくらいで、大ホールでは考えられないような距離感です。学生さんには、ぜひもっと知ってほしいですね。
現在、この音楽祭は寄付金によって運営されていると伺いました。今後どのような支援や設備が必要ですか?
そもそも演奏者への謝礼や会場の準備、スタインウェイのピアノのレンタル等で、かなりの費用がかかりますので、ご寄付の力は不可欠です。今後、一流の演奏者を継続的に招聘するためにも、今は目標金額に向けて基金を募っている最中です。音楽祭の安定的な継続自体が目標ですが、それ以上のご支援がいただければ、若手演奏者を招いてより気軽に楽しめるような小規模なイベント等を開催や、設備の充実を図りたいと考えています。
最後に、音楽祭に興味のある方や、基金への寄付を検討されている方へのメッセージをお願いします。
最初にお話ししたことに戻りますが、「科学と芸術は、目指すところは同じ」との想いのもと、駒場第二キャンパスにおいて「科学と芸術が近くにある環境」を作っていきたい、と願っています。東大をより、魅力ある場としたいと思います。そのためには、みなさまのご支援が不可欠です。どうぞよろしくお願いいたします。

音楽祭体験レポート
戸矢先生の東大の学生にとって音楽が身近にある環境を作っていきたいという熱い想いを聞き、期待に胸を膨らませて、私は音楽祭が行われるS 棟プレゼンテーションルームに向かいました。
「観客を置いて行かない」仕掛け──近藤先生の解説
本コンサートで最も印象に残ったのは、演奏と演奏の合間に司会を務めた近藤薫先生による解説が挟まれていたことです。先端研の中でも屈指のお話好きとして知られる先生の語り口はユーモアに富み、演奏者や楽器にまつわる専門的な話題を、初心者にも分かりやすく、そして興味深く伝えてくださいました。
特にクラシック音楽に馴染みのない私にとって、こうした解説があることで、ただ音楽を“聴く”のではなく、楽器の背景や作曲家の意図を理解しながら“味わう”ことができました。「知る」ことが「聴く」ことの楽しさを増幅させる、そんな体験でした。

弦と管、それぞれの魅力を経て、オーケストラへ
コンサートは、弦楽器と管楽器、それぞれのアンサンブルから始まりました。個々の楽器の音色が持つ独特の魅力や、少人数編成ならではの繊細なアンサンブルが際立ち、楽器ごとの特性をじっくりと味わうことができました。
中でも印象的だったのは、メシアン作曲《峡谷から星々へ》の中の一曲「恒星の呼び声」。現代音楽ならではの不協和音や複雑なリズムを通して、宇宙的な広がりと人間の根源的な叫びのようなものが交錯し、深く心に残りました。さらに、演奏者が2階の後ろから演奏をするという特別な演出も行われました。
そして最後に演奏されたのは、R.ワーグナーの《ジークフリート牧歌》。弦と管が一体となって織りなす柔らかくも壮大な響きは、これまで個別に聴いてきた楽器の音がどのように全体のハーモニーの中で機能しているかを浮かび上がらせ、まさに総合芸術としてのオーケストラの醍醐味を感じさせてくれました。

音と空間の融合──S 棟プレゼンテーションルームという舞台装置
この特別な音楽体験をさらに引き立てていたのが、生産研の今井公太郎教授が設計した駒場リサーチキャンパス 「S 棟プレゼンテーションルーム」でした。普段は講義やセミナーが行われているとは思えないほど、音響・照明ともに優れた設備が整えられており、音がホール全体に豊かに響き渡りました。
演奏がクライマックスへ向かうにつれ、演奏者の身体の動きや弓の軌跡がより大きくなり、それと連動して音楽の迫力も増していく──その一体感を視覚的にも感じ取ることができたのは、生演奏ならではの醍醐味であり、このホールの設計がそれを可能にしていることは間違いありません。
まるで、科学と芸術が融合した「空間そのものが一つの作品」であるかのようでした。

芸術への目が開くということ──私自身の変化
この音楽祭を通して、私の中に確かな変化が生まれました。それは、芸術に対する視野が広がったことです。
もともと私は作業中に映画音楽のオーケストラ版をBGMとして流すことが多かったのですが、今回の体験以降は、「どの楽器がどの旋律を担っているのか」「どのように音が重なっていくのか」といった点に意識が向くようになりました。さらに、音だけでなく、演奏者の息遣いや身体の動きといった“演奏の全体像”を映像で観ることにも興味が湧きました。
芸術の奥にある、人への関心が私の中で芽生えたように感じました。
未来に向けて──他の学生へのメッセージ
科学と芸術は対立するものではなく、むしろ互いを深め合う存在なのかもしれません。講義室でありながら劇場にもなる──今井先生が設計されたプレゼンテーションルームは、その象徴と言えるでしょう。一つの空間が多様な価値を包摂することで、人々の感性や視野を広げていくのだと実感しています。
一学生として、今回の演奏会が一流の演奏者の方々と東京大学との架け橋となり、学生に新たな学びや機会をもたらすことを願ってやみません。演奏者の方々が東大という場に親しみを感じてくださり、今後、学内イベントへの登壇や、前期課程の「全学体験ゼミナール」などの枠で授業を開講してくださるような機会が生まれれば、学生の学びはより多様で豊かなものになると希望を持っています。
※全学体験ゼミナール:学生の希望に応じて開講される特別授業。東大の外部から講師を招くこともあり、通常の講義では得られない多彩な学びを提供する。筆者はこれまでにこの授業を通じて、プロから学ぶオペラの歌唱法、アートマネジメント、インタビュー技法、メンタルヘルスなど、幅広い分野に触れてきた。