
プラネタリーヘルス研究機構(RIPH)基金
100年先への未来へ向けて
今の地球環境を俯瞰すると、地球温暖化とそれに伴う干ばつや豪雨に人類は苦しみながら日々温室効果ガスを排出し、作りすぎた食品を廃棄しながら一方で飢餓に苦しみ、物理的にも経済的にも戦争をしているという世界に私達は暮らしています。 このような社会が続き、環境負荷が蓄積されれば、やがて私達自身が地球で健康的に暮らすことができなくなります。しかし、それを誰もが分かっていながら、未来の地球および人類の健康に向けて何もアクションができないというのが現状ではないでしょうか。
この課題に対応するため、東京大学は東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)と100年間の産学協創協定を結び、高輪ゲートウェイシティに「東京大学GATEWAY Campus」を開設しました。同時に、地球と人類の健康を目指す「プラネタリーヘルス」をテーマとした「Planetary Health Design Laboratory(PHD Lab.)」を立ち上げました。
「プラネタリーヘルス」とは、ヒトの健康だけでなく地球における生物圏全体の健康を目指す概念ですが、プラネタリーヘルスを達成するためには時間的に長いビジョンが必要となります。
「東京大学プラネタリーヘルス研究機構(UTokyo RIPH)」は、このようなプラネタリーヘルスに関わる活動全般を東京大学が支える仕組みで、異なる研究科に所属する教員が分野横断的に共同研究を行いながら、多様性(Diversity)と包摂性(Inclusion) さらに国際性(internationality)を重視し、プラネタリーヘルスを達成するために様々な活動に取り組んでいます。
東京大学プラネタリーヘルス研究機構 機構長 五十嵐 圭日子

「東京大学GATEWAY Campus」から生まれる人・街・地球にやさしい未来のくらし
私たちが目指す未来の暮らしは、単なる技術革新だけでは実現できません。気候や食、生活環境に関わる多様な課題に取り組むには、分野を超えた研究と継続的な資金が欠かせません。
東京大学GATEWAY Campusでは、TAKANAWA GATEWAYCITYを実験の場として、人・街・地球に優しい未来の暮らしを生み出します。
具体的な取り組みは以下のとおりです:

データを活用して一人ひとりに最適な食事を提案しながら、街全体の食品廃棄を減らします

約2.7ヘクタールの日本在来種を中心とした緑地で先進的な都市型緑化を行い、そこで育てた植物を材料にした商品開発から販売までの循環型経済を作ります

東京大学で開発した培養肉などの環境に優しい食材をオフィスワーカー向け食堂で提供し、利用者の意見を取り入れた新しい食材開発を進めます

最新の睡眠分析技術や体の動きを非接触で分析するシステムを活用した健康サービスを提供します

マルハニチロとJR東日本との協創プロジェクト
これらの新しい取り組みには、安定した研究資金が欠かせません。短期間の研究助成だけでは対応できない長期的な課題に取り組むため、皆様のご支援が必要です。
ご寄付の使途
いただいたご寄付は、以下の活動に活用させていただきます:
- 持続的で柔軟な研究基盤の整備
- プラネタリーヘルスという新しい学問分野の普及・情報発信
- 未来を導く次世代のリーダー、研究者、イノベーション人材の育成
プラネタリーヘルスは比較的新しい学問分野です。これを社会に根付かせ、地球規模の課題解決につなげるには、研究活動の充実とともに、積極的な情報発信や人材育成が欠かせません。皆様のご支援により、長期的かつ安定した取り組みが可能になります。
ご寄付によって実現できること
皆様からのご支援により、地球と人類の健康が共に守られる未来に向けた研究と社会実装が進み、次のような成果が期待できます:
- 気候変動、感染症、食料問題などに対する具体的な解決策の提案
- 環境・健康政策に役立つ政策提言の発信
- 新しい都市・生活様式モデルの構築と世界への発信
- 100年後の地球における「人と自然の共生」の実現
- 誰もが健康に暮らせる持続可能な社会の構築
- 日本発の学術的・社会的リーダーシップの発揮
ご寄付は、単なる研究支援にとどまらず、地球規模の課題解決と持続可能な未来の創出に直接つながります。
東京大学プラネタリーヘルス研究機構へのご支援を、どうぞよろしくお願い申し上げます。


が、しかし、脳みそはクリアに整理されていますのでご安心ください。
関連リンク
東京大学GATEWAY Campus開所式に行ってきました!(東大生がレポート!)
2025年12月16日(火)

はじめに
東京大学は2023年、JR東日本と「プラネタリーヘルス」の創出を目指す協創プロジェクトPlanetary Health Design Laboratory(PHD Lab.) のビジョンのもと、100年間の産学協創協定を締結しました。その取り組みの一環として、高輪ゲートウェイシティに「東京大学 GATEWAY Campus」 が開設され、同キャンパスを拠点に活動する組織として 東京大学プラネタリーヘルス研究機構 が発足しました。
2025年10月21日(火)、その開設を記念したオープニングセレモニーが開催されました。今回は、学生ファンドレイジングサポーターの私・ゆめが、その様子をレポートします!
東京大学 GATEWAY Campusに到着!
高輪ゲートウェイ駅を出てすぐの建物に足を踏み入れた瞬間、まず感じたのはそのスケールの大きさ。「ここから東大と企業の新しいコラボレーションが動き出すのか!」と思うと、ワクワクしました。
(なお、私は授業の都合により午前の式典には参加できませんでしたので、午後のイベントを中心に取材させていただきました。キャンパス内の様子は、別の機会に改めてレポートしたいと思います!)
高輪ゲートウェイシティには「100年先の心豊かなくらしのための実験場」というコンセプトのもと、環境・モビリティ・ヘルスケアの3つの重点テーマに取り組むため、LiSH:TAKANAWA GATEWAY Link Scholars’ Hub が整備されています。
JR東日本が主導するこの施設には、企業やスタートアップ、研究者など多様なプレイヤーが参画し、 東京大学をはじめとするアカデミアの知見も取り入れながら、アイデアを社会実装へとつなげていくことを目的としています。
ここは、多様で先端的な知や技術をつなぎ合わせ、新たなビジネスや文化を生み出すことを目指す“ビジネス創造施設”。
セミナーやワークショップを行うスタジオ、環境・ヘルスケアに関する基礎研究を行う実験室なども備わっています。
――「都心の駅ビルにこんな設備が!?」 と驚くような空間が広がっていました。
午後は、オープニング記念セッションへ
セッション前半のクロストークでは、東京大学プラネタリーヘルス研究機構の潮教授、東日本旅客鉄道株式会社の高木常務執行役員、マルハニチロ株式会社の小関常務執行役員により、「東大×JRE×マルハニチロによる新たな産学協創」をテーマとして議論がされました。
「高輪という場所から、日本全国そして世界へつながることへの期待」
「多様な人たちによるディスカッションが日常的に行われ、自然と人が集まる場所になることへの期待」
「地球・社会問題の解決につながる期待」
このキャンパスに込められたたくさんの『期待』を知ることができました。
後半では東京大学GATEWAY Campus を拠点に取り組む四つの研究テーマについて、担当の教授、准教授から紹介がありました。
個人的には竹内昌治教授による『サステナブルな未来の食を試せる街×生物工学・工学』と題した、培養肉の研究が印象に残っています。
人口増加や新興国の経済成長によって地球規模で食肉需要が増加しており、従来の畜産だけでは、供給が追いつかない可能性が指摘されています。そこで登場したのが、「代替肉」。そのうちの一つ、細胞培養によって作られる「培養肉」は期待される技術ですが、これまではミンチ肉のような、ランダムに並んだ筋肉の細胞を集めたものが主流でした。竹内教授らのチームは3 次元筋組織作製の方法を活かし、ウシ細胞を使って筋線維が配向した、「ステーキ肉」の作製に成功したとのこと。もちろん食べても安全で、実際に焼くと「肉のとてもいい香りがした」とのことですが…、口に入れてみると美味しくなかったという率直な感想を述べられていました(笑)
私は農学部出身で、食糧生産に関する講義もたくさん聞いてきたので、興味津々でした。さらなる研究が進んで、“美味しい”培養肉が開発され、サステナブルな食の未来が実現することを願っています。私もいつか試食してみたいです!
さいごに
今後高輪ゲートウェイには1日あたり10万人以上が訪れることが想定されています。たくさんの人が行き交う場所に東大と社会との接点になる場所ができたことに、在学生として大きな魅力を感じました。そして、このキャンパスがもたらす産学協創の発展を、ただ“見守る”だけではなく、私自身も積極的に関わり、未来をつくる側の一員になりたいと思いました。今後の東京大学GATEWAY Campusの展開が楽しみです!
創設記念式典と内覧会を開催!
2025年11月07日(金)

2025年10月21日に東京大学GATEWAY Campus・プラネタリーヘルス研究機構の創設記念式典と内覧会、午後には企業様向けオープニング記念セッションを行いました。
午前は217名、午後は96名の皆様がご参加くださいました。お忙しい中のご参加、ありがとうございました。




式典の詳細については、以下のリンクをご覧ください。東京大学GATEWAY Campusオープニングセレモニー
WBSで放映されました(YouTube)
東大 高輪に新キャンパス JR東とタッグ【WBS】

















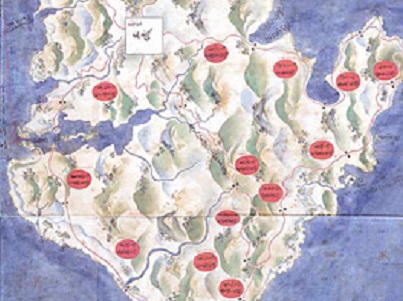





















<プラネタリーヘルス研究機構(RIPH)基金>
<プラネタリーヘルス研究機構(RIPH)基金>
<プラネタリーヘルス研究機構(RIPH)基金>
<プラネタリーヘルス研究機構(RIPH)基金>