
未来ビジョン研究センター
センター長からのメッセージ
未来ビジョン研究センターは、「東京大学の知性を結集した世界的なネットワークの拠点として、地球と人類社会の未来に関連する学際的かつ社会連携型の研究を推進し、持続可能な未来ビジョンの創造に広く寄与すること」を目的として2019年4月に設置され、これまで、多様な研究者が専門分野を超えて連携し、現代世界の抱える課題に取り組み、その成果を政策提言・社会提言などを通じて社会にフィードバックする活動を行ってきました。
2023年の春に創設5年目を迎えることを機に、研究部門の構成を7つから4つに再編しました。政治学・開発学・工学等の分野横断的な知見を生かしてグローバルな複合的リスクにアプローチする「地球規模ガバナンス研究部門」、アクション・リサーチ(課題解決型実証研究)を通じて協創・共学習の場としてコミュニティを再構築し、複合的な社会課題に横断的・自律的に対処可能な社会システムのガバナンスを実装する「コミュニティ協創研究部門」、科学技術イノベーションの政策・経営・社会デザインに関する学理の創出と、適切な技術の社会実装を目指す「イノベーション・ガバナンス研究部門」の3つの研究部門を新設し、民間企業や他大学等との連携を推進する「共同研究・寄付研究部門」を加えた4研究部門により研究活動を行います。今回の部門再編の目的は、研究者間の交流を促し、イノベーションを創出すると同時に、部門としてのアウトプットを大きくしてビジビリティを高めることです。また、部門の集約により、組織としての活動の方向性をより明確に打ち出していきたいと考えています。

創設後の4年間の多くはCOVID-19の影響下での活動であったため、海外研究機関との連携、自治体や地域のステークホルダーとの共同研究、フィールド調査等の活動が制約されてきましたが、ITを活用しつつ、シミュレーションや理論研究等の研究活動を精力的に進めてきました。加えて、グローバル・コモンズ・センター(CGC)の設置、著名学術誌と連携したシンポジウムの開催等、国際的にインパクトの高い活動も行ってきました。未来ビジョン研究センターにおける重要な活動は、研究者コミュニティだけではない多様なステークホルダーとの対話であり、それを通じて新しい考え方や研究分野の開発、社会実装に繋がるような研究をco-designしていくことにあります。パンデミックの終結が見えてきた中で、その間に得られた数々の新しいコミュニケーションの方法と、さまざまな形で人と人とが直に接する活動を組み合わせることで、本センターの研究活動をいっそう充実させていきます。中でも国際的なパートナーシップを構築するような活動を重点的に推進したいと考えています。
このような活動は、学術知識を活かした課題解決への貢献、社会への新たな政策の発信、さらに課題解決を先導する人材育成の必要性を感じておられるすべての方のご支援、ご協力により、初めて可能となります。そのためには経済的な基盤も必要です。多くの方に本センターの活動にご関心をお持ちいただくとともに、今後とも一層のご支援、ご協力を賜りますよう、お願いいたします。
センター長 福士 謙介
2025年活動報告
-産官学民の連携のハブとしての役割を果たし、研究に基づくよりよい未来社会を実現する選択肢を示す-
2026年01月27日(火)
未来ビジョン研究センター(IFI)は2019年4月に政策ビジョン研究センター(PARI)と国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)の両部局が発展的に統合する形で設置されました。IFIでは、持続可能な未来社会を創造するために、未来社会の諸課題に関する政策・社会提言ならびにそのための研究を社会と連携して行っています。また、未来社会に関連する大学の知見を統合する国際ネットワーク・ハブおよび産官学民との協創のプラットフォームとしての役割を果たし、研究に基づいた未来社会を実現する選択肢を示すとともに、これらの活動の担い手となる人材の育成にも貢献しています。2023年4月に研究部門を再編し、現在は「地球規模ガバナンス」「コミュニティ協創」「イノベーション・ガバナンス」「共同研究・寄付研究」の4つの分野横断型の研究部門により研究を進めています。
IFIは、東京大学の持続可能な開発目標(SDGs)に向けた取り組みの枠組みである未来社会協創推進本部(Future Society Initiative, FSI)、また、東京大学が目指すべき理念や方向性をめぐる基本方針であるUTokyo Compassに掲げる理念の実現を加速させることを任務とするUTokyo Compass推進会議(UTokyo Compass Initiative)の中核的組織として位置付けられています。
(1)研究を通じて発信された社会課題に関する提言
今年度は、SDGs協創研究ユニットより、2021年12月からの3年間に実施した研究プロジェクト「ダウンサイドリスクを克服するレジリエンスと実践知の探究-新型コロナ危機下のアフリカにおける草の根の声」の成果として、 「サハラ以南のアフリカにおける感染症対策に関する政策提言」を発信しました。本提言は、感染症対策がもたらすリスク・トレードオフへの対策の必要性、感染症対策の政治化による民主主義の危機への警戒、誤情報を対処・是正するための標的を絞ったコミュニケーション戦略の必要性、レジリエンスの源泉としてのインフォーマル・ネットワーク支援の必要性を掲げ、より大局的な視座で将来のパンデミックに備えることを目指して、特にアフリカへの援助政策を実施する国連・国際機関や各国政府援助機関へ向けて発信しました。
また、グローバル・コモンズ・センター(CGC) では SYSTEMIQ社と協働した政策提言「Making Natural Capital Count: An Investment Agenda」並びに社会提言「日本の化学産業のサステナブルな事業モデルへの移行に関する提言」を発信しました。これらの提言は、CGCが2020年から実施してきた海外パートナーとの協働イニシアチブである「グローバル・コモンズ・スチュワードシップ・イニシアチブ(Global Commons Stewardship Initiative)」の活動の一環として作成しています。
前者は、「ブラジルCOP30で発表された気候金融に関する独立ハイレベル専門家グループ(IHLEG)の第4報告書」を補完するものであり、自然資本の価値を経済システムに組み込む――その結果「自然がバランスシートに載るようになる」――という新たな経済・金融システム構築の必要性を示すうえで、システム転換を促進する要因として、政策、会計システム、金融商品などが相乗効果をもたらし、既存制度の構造的な改革を加速させるという分析をもとに、世界の意思決定者に向けて政策提言を行っています。
また、後者は、日本の産業界の中で鉄鋼業に次ぐ温室効果ガス (GHG) 排出源である化学産業に焦点を絞り、基礎化学製品からのGHG排出をネットゼロにする道筋を定量的に算出した査読論文と日本の化学産業に関する知見を統合し、ネットゼロ実現のための戦略やアクションを示しました。本提言は、特に企業に対して発信すると共に、日本と同様の制約に置かれた他国・地域にも適用できると考えています。

キャプション:グローバル・コモンズ・センターによる、政策提言「Making Natural Capital Count: An Investment Agenda」および社会提言「日本の化学産業のサステナブルな事業モデルへの移行に関する提言」
(2)未来社会の創造に向けたフロントライン・プロジェクト
IFIでは、2025年も産学・官学連携プロジェクトを推進し、各分野のフロントラインにおいて着実な成果をあげています。本項では、特定基金に支えられた継続的な取り組みである、高齢化社会におけるフレイル予防と包摂的コミュニティの共創に焦点を当てて報告します。本年度は、これまでの成果を基盤とし、フレイル予防の社会実装と包摂的コミュニティの恒久化に向けて挑戦的な1年となりました。
【高齢化社会におけるフレイル予防プロジェクトと包摂的コミュニティ共創への加速】
人生 100 年を設計する超高齢社会まちづくり研究ユニットでは経年にわたり、生活習慣病の管理による狭義のヘルスケアではなく、健康長寿と生きがいも含めたウェルビーイング向上を兼ね備えた「幸福長寿」を実現できる地域づくりを目指しています。高齢化が加速するなかで、地域づくりの一環として、高齢者個人および地域全体の虚弱化(フレイル)を予防しながら健康長寿と幸福長寿の両立を実現するために、最新エビデンスに基づいた課題解決型実証研究(アクションリサーチ)を主軸に置き、「住民主体でのフレイル予防を軸とした街づくり戦略」を最重要課題と位置付けて取り組んでいます。
これまでの取り組みでは、大規模縦断追跡コホート調査研究により、特に高齢者(なかでも後期高齢者)において栄養(食事と口腔機能)・身体活動(運動や生活活動)・社会参加の3つの柱がフレイル予防の中核であり、三位一体での底上げを目指すことで大きくフレイル予防につながることをエビデンスで証明し、住民主体による健康長寿まちづくり戦略の全国プラットフォームを構築してきました。また、これに付随する身近な重点課題が『脱水』であり、体内が軽微の脱水状態に徐々に傾き始めているにも関わらず自覚のない「隠れ脱水」に陥ると、様々な身体機能が負の連鎖を起こし、最終的に生活不活発状態を経由して身体機能低下に陥りやすくなります。本取り組みでは、この隠れ脱水の問題を「①大規模な広報戦略、②地域コホート研究におけるデータ解析、③包摂的地域コミュニティ構築」の複数の視点から多角的にアプローチするため、貴重な本寄附金を活用して、産学連携の共同研究開発のアクティビティを加速させています。
すでに2024年度においては、秋季に実施した千葉県柏市をモデルフィールドとした大規模高齢者縦断追跡コホート調査研究(=柏スタディ)13年目の第8次調査において、多面的かつ膨大なデータとともに、脱水関連のデータおよびペットボトル形状やキャップ開閉関連のデータを取得しました。2025年下半期には、アンケート質問票による第9次調査を実施し、データを収集中です。これらの研究によって、脱水とフレイル現象の関係性、水分補給の重要性と高齢者の認識具合い、筋肉減弱症(サルコペニア)状態の高齢者におけるペットボトル形状やキャップ開閉のあり方など、今後の飲料推奨における多面的アプローチが可能となると考えております。また、リビングラボ戦略を基盤とした包摂的コミュニティ共創の視点から、2025年には、実際の高齢者(合計14名)に対してナラティブインタビュー調査などを実施し、個々の住民の経験や課題を掘り下げた有益なデータを取得しました。具体的には、日常生活内での水分補給の考え方やそのタイミング、飲料の選別の視点やペットボトルの形状(特にキャップ開閉問題)、高齢者にとっての飲料全般への課題と希望内容など、多面的な視点で生活者からの生の意見を聴取し、同対象者に対して、日常でのスーパーマーケットでの購買行動への密着同行まで実施しました。これらの新たなデータ収集(量的、質的の両方)から新エビデンスを見出し、大規模な広報を含めかなり踏み込んだ戦略を進められることを期待しています。次年度(2026年度)の秋には、再び大規模高齢者健康調査(柏スタディ第10次調査)を予定しており、前述で得られた知見をさらに深掘りしていく予定です。それによって、具体的な地域フィールドにおける住民主体活動などにも落とし込み、住民目線を十分に踏まえた脱水対策の次世代型地域コミュニティ研究開発を実現することが出来ると考えております。フレイル予防研究の一環である高齢者の多層的な隠れ脱水対策を通して、次世代型の包摂的コミュニティの共創に今後も大きく貢献して参ります。


(3)「次世代を担う中核人材の活躍促進」
IFIではハブ組織としての特異性を活かして、国内の官民との共同研究・協働事業を促進することで優秀な若手研究者のポジションを確保し、研究を軸に社会基盤を再構築する次世代の中核人材を後押ししています。2021年に発足したダイキン工業との社会連携研究部門「理想の空気を持続するサーキュラーエコノミービジネスモデル連携研究ユニット」の共同研究ではプロジェクトにかかわる人材の長期雇用・拡充を実現し、研究も過年度の報告から引き続き順調に実施しています。また、同2021年に発足したトヨタ財団との協働事業「つながりがデザインする未来の社会システム」では、人と人、人と自然、人とモノ・技術といった様々な関係性をつなぐ学際的な分野においてキャリア萌芽期の研究者を後押し、各分野での順調なキャリア形成につなげています。
(4)IFIを身近に感じていただくために
IFIにはさまざまな分野にわたって第一線で活躍している研究者が在籍しています。社会課題解決のための研究に興味を深めていただくきっかけとして、2025年度には、昨年に続きオープンキャンパスで「東大研究者に聞く10の質問 & 先生の研究を教えて!」と題する動画を配信しました。当センターをより身近に感じていただける内容となっていますので、ぜひご覧ください。
経過報告
2026年01月15日(木)
未来ビジョン研究センター(IFI)は2019年4月に政策ビジョン研究センター(PARI)と国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)の両部局が発展的に統合する形で発足し、本特定基金にもまた、長くセンターの活動をご支援いただいております。これまでにご寄付いただいた方々に、心より感謝申し上げます。
IFIでは、持続可能な未来社会を創造するために、社会の諸課題に関する政策・社会提言ならびにそのための研究を、社会と連携して行っています。また、未来社会に関連する大学の知見を統合する国際ネットワーク・ハブおよび産官学民との協創のプラットフォームとしての役割を果たし、研究に基づいた未来社会を実現する選択肢を示すとともに、これらの活動の担い手となる人材の育成にも貢献しています。創設後の約4年間はCOVID-19の影響下での活動となり、海外研究機関との連携、活動等が制約されたものの、2020年8月に設置したグローバル・コモンズ・センター(CGC)の地道な提言活動をはじめ、国際的な足場も着実に固めてきております。
また、IFIは、2023年度より、地球規模ガバナンス研究部門、コミュニティ協創研究部門、イノベーション・ガバナンス研究部門、共同研究・寄付研究部門の4つの研究部門に再編成して活動しており、本特定基金でのご支援も活用し先進的なプロジェクトを推進しております。特に、フレイル予防を軸とした健康長寿・幸福長寿まちづくりの実現に向けた研究(コミュニティ協創部門、人生100年を設計する超高齢社会まちづくり研究ユニット)においては、本特定基金による著しい活性を享受しており、改めてご寄付に感謝申し上げます。
本研究では、高齢者の虚弱化(フレイル)予防による健康長寿の実現を、栄養(食事と口腔機能)・身体活動(運動や生活活動)・社会参加の3つの柱がフレイル予防の中核となることをエビデンスで証明し、住民主体による健康長寿まちづくり戦略の全国プラットフォームを構築してきました。また、これに付随する身近な課題として、高齢者の「隠れ脱水」による負の連鎖を防ぐべく、意識啓発や地域コミュニティ自体の適切な水分補給支援の環境整備に着目しています。
経年にわたり大規模コホート研究を継続すると共に、具体的な地域フィールドにおける住民主体活動などへの落とし込みを行い、さらにはリビングラボ的な発想のもと、住民目線を十分に踏まえた脱水対策の次世代型地域コミュニティ研究開発の実現を目指しています。今後も、多層的なフレイル予防研究における高齢者の隠れ脱水対策、また、包摂的なコミュニティの共創による研究を加速させて参ります。
これまでのご寄付による成果を踏まえて、本特定基金を今後も継続し、センターの活動をさらに活性化させていきたいと考えています。未来ビジョン研究センターでは、2024年に行った自己点検・評価を受けて、「世界的ネットワーク型拠点形成機能の強化」も視野に入れています。
この取り組みを発展させるうえでも大いに関連するのが、若手人材の育成です。人材育成に関しては全学的にも積極的な啓発や支援が行われておりますが、未来ビジョン研究センターでは独自の教員学外研修支援制度を設置し、国際的な研究者間ネットワークの拡充が得られるよう後押ししております。この制度には、本特定基金での支援が大いに活かされています。
センター全体としての新しい試みの加速や若手人材の育成は、特定基金があってこそ具現化できるものです。世界情勢が不安定になる中、人類共通の課題に継続的に取り組む未来ビジョン研究センターの活動が明るい未来につながるよう、今後も邁進していきます。
2024年活動報告
-産官学民の連携のハブとしての役割を果たし、研究に基づくよりよい未来社会を実現する選択肢を示す-
2025年01月30日(木)
未来ビジョン研究センター(IFI)は2019年4月に政策ビジョン研究センターと(PARI)と国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)の両部局が発展的に統合する形で設置されました。IFIでは、持続可能な未来社会を創造するために、未来社会の諸課題に関する政策・社会提言ならびにそのための研究を社会と連携して行っています。また、未来社会に関連する大学の知見を統合する国際ネットワーク・ハブおよび産官学民との協創のプラットフォームとしての役割を果たし、研究に基づいた未来社会を実現する選択肢を示すとともに、これらの活動の担い手となる人材の育成にも貢献しています。2023年4月に研究部門を再編し、現在は「地球規模ガバナンス」「コミュニティ協創」「イノベーション・ガバナンス」「共同研究・寄付研究」の4つの分野横断型の研究部門により研究を進めています。
IFIは、東京大学の持続可能な開発目標(SDGs)に向けた取り組みの枠組みである 未来社会協創推進本部(Future Society Initiative, FSI)、また、東京大学が目指すべき理念や方向性をめぐる基本方針であるUTokyo Compassに掲げる理念の実現を加速させることを任務とするUTokyo Compass推進会議(UTokyo Compass Initiative)の中核的組織として位置付けられています。
(1)研究を通じて発信された社会課題に関する提言
今年度は、地球規模ガバナンス研究部門から、エネルギー分野に関する提言を2件発信しています。「洋上風力発電に関する分野を超えた開発政策の提案 港湾/港湾都市の視点から 」の政策提言では、洋上⾵⼒産業の関係者が直⾯しているリスクや障害、また政府への期待などについて調査、分析し、国が掲げる洋上⾵⼒開発⽬標を実現するために、中央政府レベルで議論し取り組むべき4つの点を整理し、提⾔を⾏いました。
次世代スカイシステム研究ユニットでは、「航空分野のCO2削減に向けた水素利用に関する提言」を発信しました。航空分野における2050年カーボンニュートラルの達成は、複数の技術革新と、それらを社会に実装するための制度改革を同時に進める必要がある非常に大きな挑戦です。その長期的なソリューションとして注目されている水素利用に焦点を当て、日本が国際的なリーダーシップを発揮し、技術開発や政策策定の面で世界の航空分野における持続可能な未来の構築に貢献するため、また、目標達成に向けて水素利用を促進するための6つの要件とそれを実現するための提案を示しています。
グローバル・コモンズ・センター(CGC)では、「グローバルと各国の環境政策のための共同マイルストーンについての政策提言: グローバル・コモンズ・スチュワードシップ(GCS)指標2024年版の公表」と、「グローバル・コモンズを守るためのエネルギー、土地利用、生産および消費の変革に関する提言」を発信しました。これらの提言は、CGCが2020年から実施してきた、海外パートナーとの協働イニシアチブである「グローバル・コモンズ・スチュワードシップ・イニシアチブ(Global Commons Stewardship Initiative)」の活動の一環として作成されました。前者は、グローバル・コモンズ(人類の繁栄と安全の土台である、安定的で回復力のある地球システム)に影響を与える国内負荷と国境を越えた負荷(波及効果)に関する最新データを示しています。 また、後者は、人類の活動により、すでにいくつかの地球システムがプラネタリー・バウンダリーによって定義された限界値を逸脱しています。本提言では、公共交通機関の電化等、主な対策を挙げて、エネルギー、土地利用、生産および消費パターンの変革を協奏的に実施できれば、気候、氷床、海洋、オゾン層、陸上生物圏すべてを保護し、グローバル・コモンズの完全性を維持し、「プラネタリー・バウンダリー」の安全領域に留まることができると提言しています。

(2)高齢化社会におけるフレイル予防プロジェクトと包摂的コミュニティ共創への加速
人生 100 年を設計する超高齢社会まちづくり研究ユニットでは、高齢化の急速な進行に加え、虚弱化(フレイル)を予防して健康長寿を実現するために、最新エビデンスに基づいた課題解決型実証研究(アクションリサーチ)を主軸に置きながら、「フレイル予防」を最も重要な課題と位置付けて取り組んでいます。
特に高齢者(なかでも後期高齢者)において、大規模縦断追跡コホート調査研究により、栄養(食事と口腔機能)・身体活動(運動や生活活動)・社会参加の3つの柱がフレイル予防の中核となることをエビデンスで証明し、住民主体による健康長寿まちづくり戦略の全国プラットフォームを構築してきました。そこに付随する身近な課題が『脱水』であり、特に高齢者ではこの脱水が些細な理由から負の連鎖を生む大きなキッカケになりやすいと考えています。体内が軽微の脱水状態に徐々に傾き始めているにも関わらず、ちょっとした兆候を自覚しにくくなり、いわゆる「隠れ脱水」の状態に容易に陥ります。このように、隠れ脱水の段階から早めに水分補給による改善を試み、平時から水分補給の管理をしっかりと行わないと、加速的にフレイル状態へ陥る、もしくはフレイル状態がさらに悪化していく可能性が高くなります。このことから、「隠れ脱水」については、いかに日常生活の中で、隠れ脱水による身体状態の負の連鎖、こまめな水分補給の重要性、高齢者自身がそれらを理解し意識変容を起こすのか、さらには、周囲の者も含めて地域コミュニティ自体が適切な水分補給を支援できる環境を醸成できるのか、さらには、高齢者を含んだ多様なバックグランドを持つ地元住民皆が、生き生きと安心して暮らせる包摂的なコミュニティ環境を共創できるのか等、多面的・包括的アプローチとして取り組むべき重要な社会課題と捉えています。
当研究ユニットでは、これらの問題を「①大規模な広報戦略、②地域コホート研究におけるデータ解析、③包摂的地域コミュニティ構築」の複数の視点から多角的にアプローチするため、貴重な本寄附金を活用して、産学連携の共同研究開発のアクティビティを加速させていきます。
すでに2024年度においては、10月~11月にかけて実施した千葉県柏市をモデルフィールドとした大規模高齢者縦断追跡コホート調査研究(=柏スタディ)13年目における第8次調査において、多面的かつ膨大なデータとともに、脱水関連のデータおよびペットボトル形状やキャップ開閉関連のデータを取得しました。2025年初頭から解析に入るところです。これらの研究によって、脱水とフレイル現象の関係性、水分補給の重要性、筋肉減弱症(サルコペニア)状態の高齢者におけるペットボトル形状やキャップ開閉のあり方など、今後の飲料推奨における多面的アプローチが可能となると考えております。また、包摂的コミュニティ共創においても関連ステークホルダーへのパネル調査やナラティブインタビュー調査などを通じて、住民一人ひとりの経験や課題を掘り下げた有益なデータを取得しました。これらの新エビデンスも十分に踏まえた上で、かなり踏み込んだ戦略及び大規模な広報戦略を進めることが出来るのではないかと期待されます。次年度(2025年度)は具体的な地域フィールドにおける住民主体活動などにも落とし込み、リビングラボ的な発想の下、住民目線を十分に踏まえた脱水対策の次世代型地域コミュニティ研究開発を実現し、多層的なフレイル予防研究における高齢者の隠れ脱水対策、また、包摂的コミュニティ共創を加速させる予定です。
(3)若手研究者の人材育成
IFIでは、2019年度の設立以来、
1.AI社会における未来ビジョンのデザイン
2.地域共生社会を支える地域循環共生圏のデザイン
3.未来社会の安全保障と平和構築に関する研究
をフラッグシッププロジェクトと位置付けて取り組み、2023年度には、1)地球規模ガバナンス、2)イノベーション・ガバナンス、3)コミュニティ協創に研究部門を再編しました。これらのプロジェクトにおいて、人と人、人と自然・地球、人とモノ・技術の「つながり」を意識した新しい展開を考え、より良い未来の社会システムをデザインするための活動として、2021年度から公益財団法人トヨタ財団との「つながりがデザインする未来の社会システム協働事業」を行っています。これまでに、3名の若手研究者の育成を行いましたが、2024年度末までに全員が転出して新たなステージに進むことになったため、今後も新たな若手研究者の育成を進める予定です。
(4)IFIを身近に感じていただくために
IFIにはさまざまな分野にわたって第一線で活躍している研究者が在籍しています。社会課題解決のための研究をより身近に感じていただけるよう、2024年度には、オープンキャンパスで「東大研究者に聞く10の質問 & 先生の研究を教えて!」と題する動画を配信しました。また、ホームカミングデイでは、「現代版イーハトーブ (理想の地) の守り方:新作講談「グスコーブドリの伝記」×アフタートーク」と題する企画を実施し、動画のオンデマンド配信を行っています。当センターの活動を身近に感じていただける内容となっていますので、ぜひご覧ください。
引き続き、当センターの活動にご支援を賜りますよう、お願いいたします。
2023年活動報告
-産官学民との連携による、よりよい未来社会の協創に向けた提言を行い、ハブとしての役割を果たす-
2024年02月21日(水)
未来ビジョン研究センター(IFI)は2019年4月に政策ビジョン研究センターと(PARI)と国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)の両部局が発展的に統合する形で設置されました。IFIでは、持続可能な未来社会を創造するために、未来社会の諸課題に関する政策・社会提言ならびにそのための研究を社会と連携して行っています。また、未来社会に関連する大学の知見を統合する国際ネットワーク・ハブおよび産官学民との協創のプラットフォームとしての役割を果たし、研究に基づいた未来社会を実現する選択肢を示すとともに、これらの活動の担い手となる人材の育成にも貢献しています。2023年4月に研究部門を再編し、現在は「地球規模ガバナンス」「コミュニティ協創」「イノベーション・ガバナンス」「共同研究・寄付研究」の4つの分野横断型の研究部門により研究を進めています。
IFIは、東京大学の持続可能な開発目標(SDGs)に向けた取り組みの枠組みである 未来社会協創推進本部(Future Society Initiative, FSI)の中核的組織として位置付けられています。
(1)研究を通じて発信された社会課題に関する提言
今年度は、昨今注目されている生成AIについて、技術ガバナンス研究ユニットからAIガバナンスに関する提言を3件発信しています。例えば、「AI ガバナンスの国際協調 欧州評議会 AI 条約の論点と⽇本の対応」の政策提言では、広島サミットで、特に生成 AI に関して、多様な規律の枠組みの調和をはかり、協調的にAI ガバナンスづくりを進めていくためG7広島AIプロセスの創設が指示されたことに関連し、法の支配等、欧州評議会で議論されている条約の締結に向けた交渉過程に、日本として確認しておくべき点を抽出して提案しています。
また、グローバル・コモンズ・センター(CGC)では、「国際的波及効果によるグローバル・コモンズへの環境負荷軽減に向けた政策提言」と「グローバル・コモンズの責任ある管理のための国際ガバナンスに関する提言」を発信しました。これらの提言は、CGCが2020年から実施してきた、海外パートナーとの協働イニシアチブである「グローバル・コモンズ・スチュワードシップ・イニシアチブ(Global Commons Stewardship Initiative)」の活動の一環として作成されました。前者は、(1)目標設定とモニタリング、(2)公共管理、(3)規制、(4)財政政策と資金調達、という4種類の国家政策レバーが、国際的波及効果にどのように作用し、問題解決に取り組むことができるかということを理解するための枠組みを提供しています。需要サイドと供給サイドの政策手段と、それらがグローバル・コモンズに与える影響について考察し、各国の政策立案者が今すぐ行動を開始するための実践的な教訓を明らかにしています。また、後者は、グローバル・コモンズの保護における国際イニシアチブの役割を理解するための枠組みを提案し、3つのシステム転換、すなわち 1)エネルギー、産業、輸送の脱炭素化、2)持続可能な食料、土地、水、海洋、3)持続可能な物質の生産と消費 を推進する国際イニシアチブの有効性を検討することで、一般的に広く理解されているグローバル・コモンズのガバナンスを大きく改善することのできる、多くの実行可能なステップを明らかにしています。
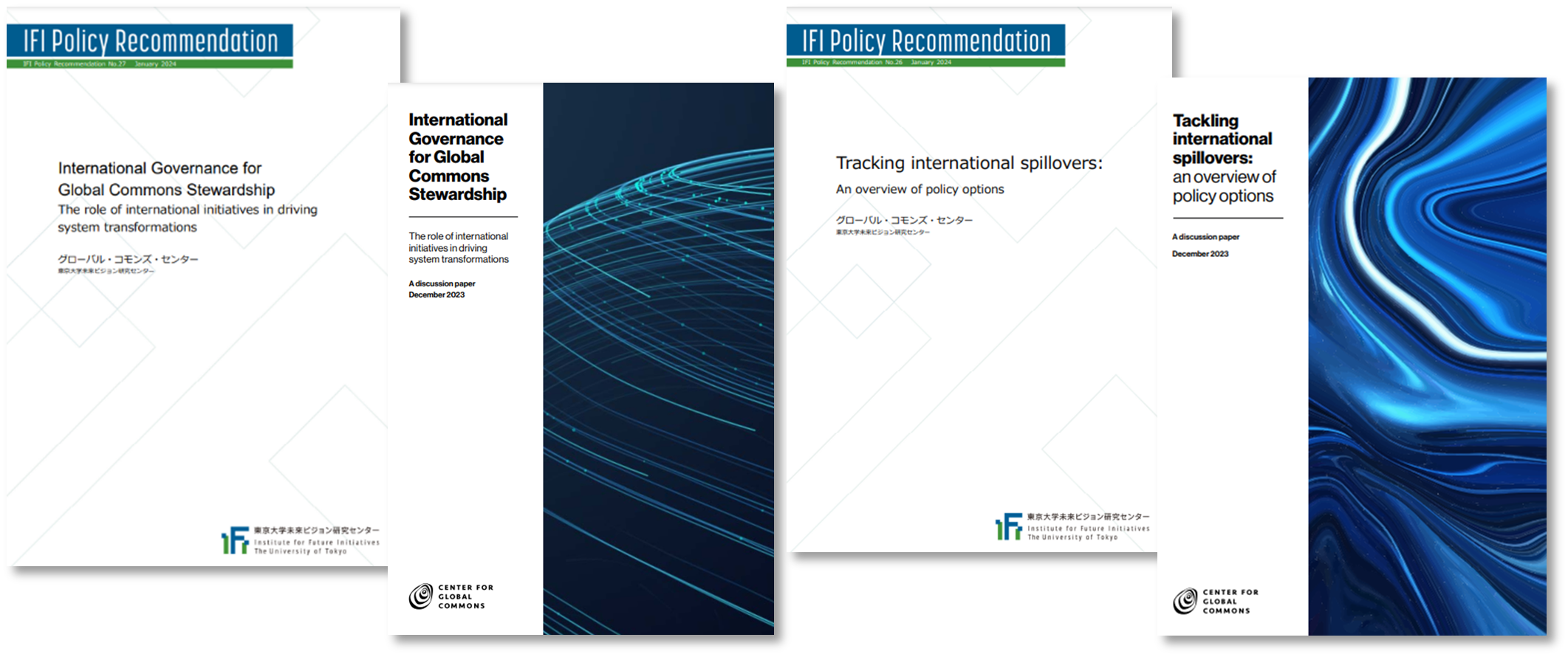
【グローバル・コモンズ・センターから発信した「国際的波及効果によるグローバル・コモンズへの環境負荷軽減に向けた政策提言」と「グローバル・コモンズの責任ある管理のための国際ガバナンスに関する提言」】
(2)高齢化社会におけるフレイル予防プロジェクトの加速
人生 100 年を設計する超高齢社会まちづくり研究ユニットでは、高齢化の急速な進行を踏まえ、健康長寿社会の実現に関する課題解決型実証研究(アクションリサーチ)を主軸にしており、その中でも「フレイル予防」を最も重要な課題と位置付けて取り組んでいます。特に高齢者(なかでも後期高齢者)において、栄養・運動を含む身体活動・社会参加の3つの柱がフレイル予防の中核となることをエビデンスで証明してきましたが、そこに付随する身近な課題が『脱水』であり、この要素が些細な理由から負の連鎖を生む大きなキッカケになりやすいと考えています。体内が軽度の脱水状態に傾き始めている際、ちょっとした兆候を自覚しにくくなり、いわゆる「隠れ脱水」の状態に容易に陥ります。このように、隠れ脱水の段階から早めに水分補給による改善を試みないと、加速的にフレイル状態へ陥る、もしくはフレイル状態がさらに悪化していく可能性が高くなります。このことから、「隠れ脱水」については、いかに日常生活の中で、こまめな水分補給の重要性や、高齢者自身がそれらを理解し意識変容を起こすのか、さらには、周囲の者も含めて地域コミュニティ自体が適切な水分補給を支援できる環境を醸成できるのか等、多面的・包括的アプローチとして取り組むべき重要な社会課題と捉えています。
当研究ユニットでは、その問題を「①大規模な広報戦略、②地域コホート研究におけるデータ解析、③地域コミュニティ構築」の複数の視点から多角的にアプローチするため、貴重な本寄附金を活用して、産学連携の共同研究開発のアクティビティを加速させていきます。
すでに2023年度においては、この大規模な広報戦略の具体案に関して、かなり踏み込んだ戦略を進めることが出来ました。次年度(2024年度)は具体的な研究開発も含めて、さらにフレイル予防研究における高齢者の隠れ脱水対策を加速させる予定です。
(3)若手研究者の人材育成
IFIでは、
1.AI社会における未来ビジョンのデザイン
2.地域共生社会を支える地域循環共生圏のデザイン
3.未来社会の安全保障と平和構築に関する研究
をフラッグシッププロジェクトとして進めていますが、これらのプロジェクトにおいて、人と人、人と自然、人とモノ・技術の「つながり」を意識した新しい展開を考え、より良い未来の社会システムをデザインするための新しい活動として、2021年度から公益財団法人トヨタ財団との「つながりがデザインする未来の社会システム協働事業」を行っています。2023年度には特任講師1名を採用し、2022年度に採用した特任研究員2名と共に若手研究者の人材育成も進めています。
(4)IFIを身近に感じていただくために
IFIにはさまざまな分野にわたって第一線で活躍している研究者が在籍しています。2023年度のホームカミングデイでは、社会課題解決のための研究をより身近に感じていただけるよう、「新作講談 × アフタートーク:GXの先駆者、本多静六の偉業」を開催し動画のオンデマンド配信も行いました。当センターの活動を身近に感じていただける内容となっていますので、ぜひご覧ください。
引き続き、当センターの活動にご支援を賜りますよう、お願いいたします。
2022年活動報告
-よりよい未来社会の協創に向けて具体的な成果を挙げていくためのハブあるいは触媒 (未来ビジョン研究センター)-
2023年02月10日(金)
未来ビジョン研究センター(IFI)は2019年4月に政策ビジョン研究センターと(PARI)と国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)の両部局が発展的に統合する形で設置されました。東京大学が、東京大学憲章に示した「世界の公共性に奉仕する大学」としての使命を踏まえ、持続可能な開発目標(SDGs)を活用しつつ、地球と人類社会の未来への貢献に向けた協創を効果的に推進する目的で設置した未来社会協創推進本部(Future Society Initiative, FSI)の中核的組織として位置付けられています。持続可能な未来社会を創造するために、未来社会の諸課題に関する政策・社会提言ならびにそのための研究を社会と連携して行い、また未来社会に関連する大学の知見を統合する国際ネットワーク・ハブおよび産官学民との協創のプラットフォームとしての役割を果たし、研究に基づいた未来社会を実現する選択肢を示すとともに、これらの活動の担い手となる人材の育成にも貢献します。現在、分野横断型の7つの研究部門、「SDGs」「サステイナビリティ学」「イノベーション」「技術・リスクガバナンス」「安全保障」「大学と社会システム」「共同研究・寄付研究」で研究を進めています。
【今年度の特徴的な活動】
(1)今年度は、グローバル・コモンズ・センター(CGC)で、「グローバル・コモンズの責任ある管理のための科学的かつ実践的なフレームワークに関する提言」を発信しました。このレポートでは、主要なステークホルダーが、グローバル・コモンズを守るためのシステム転換を駆動する際に参考となる具体的なアクションを示し、行動の呼びかけを行なっています。
(2)東京大学を代表機関とする共同研究プロジェクト共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)「ビヨンド・“ゼロ・カーボン”を目指す“Co-JUNKAN”プラットフォーム研究拠点」(Co-JUNKAN)が今年度より本格型に移行し、ネットゼロカーボンへの取り組みが、環境・生態系、食料生産、雇用、伝統・文化の発展など地域の豊かさに繋がるビヨンド・“ゼロカーボン”の実現に向けて研究活動を加速しています。本プロジェクトに豪州クイーンズランド州政府が参画していることを背景に、2022年6月に、クイーンズランド工科大学(QUT)のMargaret Sheil学長が本学に来訪し、東京大学とのさらなる連携強化に向けてIFIの城山英明センター長らと会談を行いました。
地域資源を活用したエネルギー、環境、経済のコウ(好・co-(共に))循環モデルを地域課題のソリューションとして地域と共に創出する(Co-creation) Co-JUNKANに、QUTは強い関心を示し、食料やエネルギーの問題など多くの分野で、日本とオーストラリアが抱える地域課題の共通点を特定できるのではないかという認識を共有しました。今後の連携の方向性としては、そうした共通の地域課題の解決に向けた共同研究が可能性の一つとして考えられるとして、様々な視点から意見交換を行いました。

城山センター長とクイーンズランド工科大学学長との対談より
(3)IFIでは、
1.AI社会における未来ビジョンのデザイン
2.地域共生社会を支える地域循環共生圏のデザイン
3.未来社会の安全保障と平和構築に関する研究
をフラッグシッププロジェクトとして進めていますが、トヨタ財団との共同事業「つながりがデザインする未来の社会システム協働事業」により、若手研究者の人材育成も進めています。2022年度には特任研究員2名を採用しました。
(4)IFIにはさまざまな分野にわたって第一線で活躍している研究者が在籍しています。2022年度のホームカミングデイでは、「QuizKnockと探る!未来ビジョン」と題した動画のオンデマンド配信を行いました。当センターの活動を身近に感じていただける内容となっていますので、ぜひご覧ください。
当センターの活動に引き続き応援をお願いいたします。
2021年活動報告
-「理想の空気を持続するサーキュラーエコノミービジネスモデル連携研究ユニット」を新設-
2022年04月01日(金)
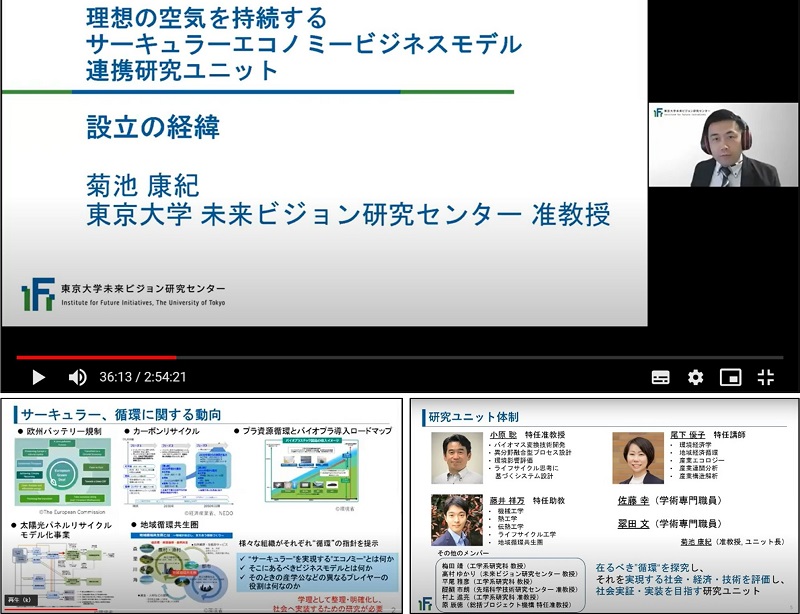
主な活動
未来ビジョン研究センターは2019年4月に政策ビジョン研究センターと(PARI)と国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)の両部局が発展的に統合する形で設置されました。東京大学が、東京大学憲章に示した「世界の公共性に奉仕する大学」としての使命を踏まえ、持続可能な開発目標(SDGs)を活用しつつ、地球と人類社会の未来への貢献に向けた協創を効果的に推進する目的で設置した未来社会協創推進本部(Future Society Initiative, FSI)の中核的組織として位置付けられています。持続可能な未来社会を創造するために、未来社会の諸課題に関する政策・社会提言ならびにそのための研究を社会と連携して行い、また未来社会に関連する大学の知見を統合する国際ネットワーク・ハブおよび産官学民との協創のプラットフォームとしての役割を果たし、研究に基づいた未来社会を実現する選択肢を示すとともに、これらの活動の担い手となる人材の育成にも貢献します。
現在、分野横断型の7つの研究部門、「SDGs」「サステイナビリティ学」「イノベーション」「技術・リスクガバナンス」「安全保障」「大学と社会システム」「共同研究・寄付研究」で研究を進めています。
2021年度に「理想の空気を持続するサーキュラーエコノミービジネスモデル連携研究ユニット」を新設しました。近年注目されている「サーキュラーエコノミー」は、採掘・加工・消費・廃棄という資源を直線的に利用する従来の経済システム(リニアエコノミー)に対し、リサイクルやリユースなど資源を循環利用することによって価値を生み出す経済の仕組みを指します。設立記念シンポジウムではサーキュラーエコノミーに必要な技術、ビジネス、法制度など研究動向についての講演やユニットの活動目標を発信しました。200名を超える皆様にご参加いただき、様々な知見を集め、世界を牽引する新たなビジネスモデルを構築するムーブメントの契機とすることができました。
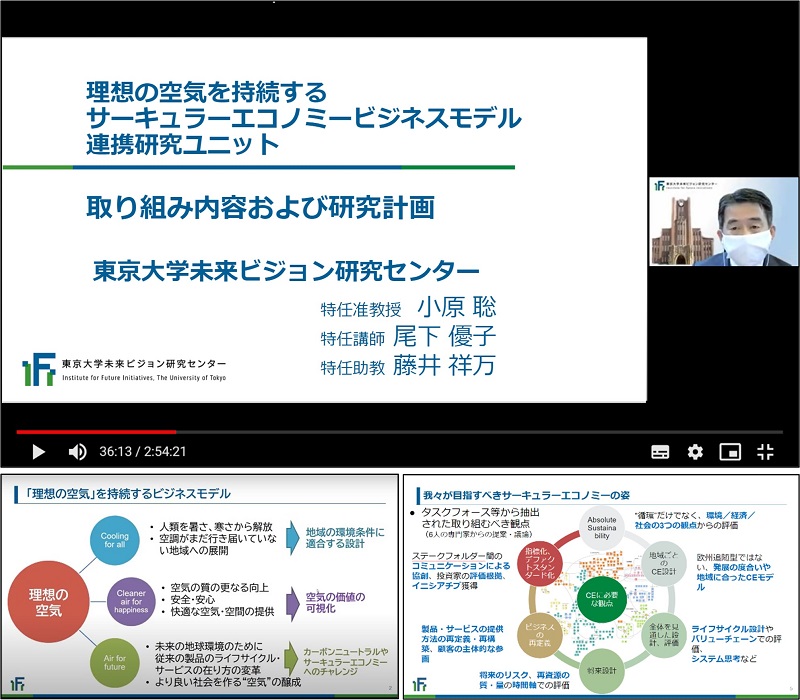
理想の空気を持続するサーキュラーエコノミービジネスモデル連携研究ユニット(IFI-CEM連携研究ユニット)設立記念シンポジウムより
また、産学及び社会連携システム研究ユニットに、スタートアップエコシステム研究プロジェクトが、立ち上がりました。大学発ベンチャーを中心とするハイテクスタートアップの研究拠点を、東京とサンフランシスコに設けて、実証分析とケース研究を行い、その比較を通じて、日本の大学発スタートアップの国際的発展のための基礎となる知見を得るとともに、その研究成果をもとに我が国のスタートアップのインバウンド・アウトバウンド施策、スタートアップエコシステムのダイバーシティーの確保等に関する政策提言を行います。
2020年8月に設置した、グローバル・コモンズ・センター(Center for Global Commons: CGC)は、100ヶ国を対象とするグローバル・コモンズ・スチュワードシップ(GCS)指標2021版を発表しました。
政策提言は、「日本の脱炭素社会への移行に関する複数モデルによるシナリオ分析の政策的知見」や「新型コロナ感染症とデータガバナンスに関する施策」など、喫緊の課題への提案も発表しています。
ご寄付の使途
いただいたご寄付は現時点では、貴重な財源として積み立てており、当センター内部の若手研究者を助成する制度(内部助成)で活用させていただく予定です。
皆様のご支援に厚く御礼申し上げます。
引き続き活動へのご理解・ご支援のほどよろしくお願いいたします。
2020年活動報告
-グローバル・コモンズ・スチュワードシップ指標(GCSi)のプロトタイプ版レポートを発表しました-
2021年02月09日(火)
主な活動
未来ビジョン研究センターは2019年4月に政策ビジョン研究センター(PARI)と国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)の両部局が発展的に統合する形で設置されたセンターです。東京大学の持続可能な開発目標(SDGs)に向けた取り組みの枠組みである未来社会協創推進本部(Future Society Initiative, FSI)の中核的組織として位置付けられています。
持続可能な未来社会を創造するために、未来社会の諸課題に関する政策・社会提言ならびにそのための社会連携研究を行い、また未来社会に関連する大学の知見を統合する国際ネットワーク・ハブおよび産官学民との協創のプラットフォームとしての役割を果たし、研究に基づいた未来社会を実現する選択を示すとともに、それを担う人材の育成にも貢献します。
現在、分野横断型の7つの研究部門、「SDGs研究」「サステイナビリティ学研究」「イノベーション研究」「技術・リスクガバナンス研究」「安全保障研究」「大学と社会システム研究」「共同研究・寄付研究」で研究を進めています。
2020年8月には、SDGs研究部門にグローバル・コモンズ・センター(Center for Global Commons: CGC)を新設し、グローバル・コモンズ・スチュワードシップ指標(GCSi)のプロトタイプ版レポートを発表しました。このレポートは国連SDSNとイェール大学、そしてグローバル・コモンズ・センターによって作成され、12月4日の東京フォーラムオンライン2020でのパネルディスカッションでも概要を発表し、話題となりました。 政策提言は、「新型コロナ感染症とデータガバナンスに関する施策」や、「AIサービスのリスク低減を検討するリスクチェーンモデルの提案」ほか、喫緊の課題への提案も発表しています。
ご寄付の使途
いただいたご寄付は現時点では、貴重な財源として未使用で積み立てており、当センター内部の若手研究者を助成する制度(内部助成)での活用など、慎重に検討のうえ活用させていただく予定です。
皆さまのご支援に厚く御礼申し上げます。
引き続き活動へのご理解・ご支援のほどよろしくお願いいたします。
2019年活動報告
-持続可能な社会の実現のために研究に基づいた政策・社会提言をおこなっています-
2020年03月13日(金)

未来ビジョン研究センターは2019年4月に政策ビジョン研究センターと(PARI)と国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)の両部局が発展的に統合する形で設置されました。東京大学の持続可能な開発目標(SDGs)に向けた取り組みの枠組みである未来社会協創推進本部(Future Society Initiative, FSI)の中核的組織として位置付けられています。持続可能な未来社会を創造するために、未来社会の諸課題に関する政策・社会提言ならびにそのための社会連携研究を行い、また未来社会に関連する大学の知見を統合する国際ネットワーク・ハブおよび産官学民との協創のプラットフォームとしての役割を果たし、研究に基づいた未来社会を実現する選択を示すとともに、それを担う人材の育成にも貢献することを目指しています。
設立後、初の政策提言として「日本企業における内部監査機能の強化に向けた政策提言」を発表しました。特に、2019年10月4日に開催した2018年ノーベル平和賞デニ・ムクウェゲ医師来日講演会 「平和・正義の実現と女性の人権」は、学内だけではなくメディアなど外部でも大きな話題となりました。詳細は https://ifi.u-tokyo.ac.jp/event/4437/ をご覧ください。

また、沖大幹教授を含む研究グループ(国立研究開発法人国立環境研究所など複数組織のメンバーを含む)が9月25日のNature Climate Change volume 9に発表した”Dependence of economic impacts of climate change on anthropogenically directed pathways”(プレスリリースタイトル:複数分野にわたる世界全体での地球温暖化による経済的被害を推計-温室効果ガス排出削減と社会状況の改善は被害軽減に有効-)など、SDGsに関するテーマの論文発表も行いました。詳細は https://ifi.u-tokyo.ac.jp/news/4740/ をご覧ください。


























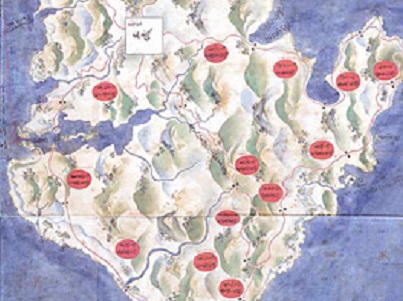




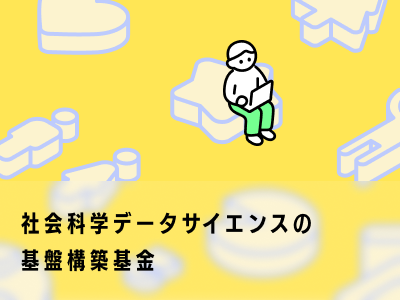

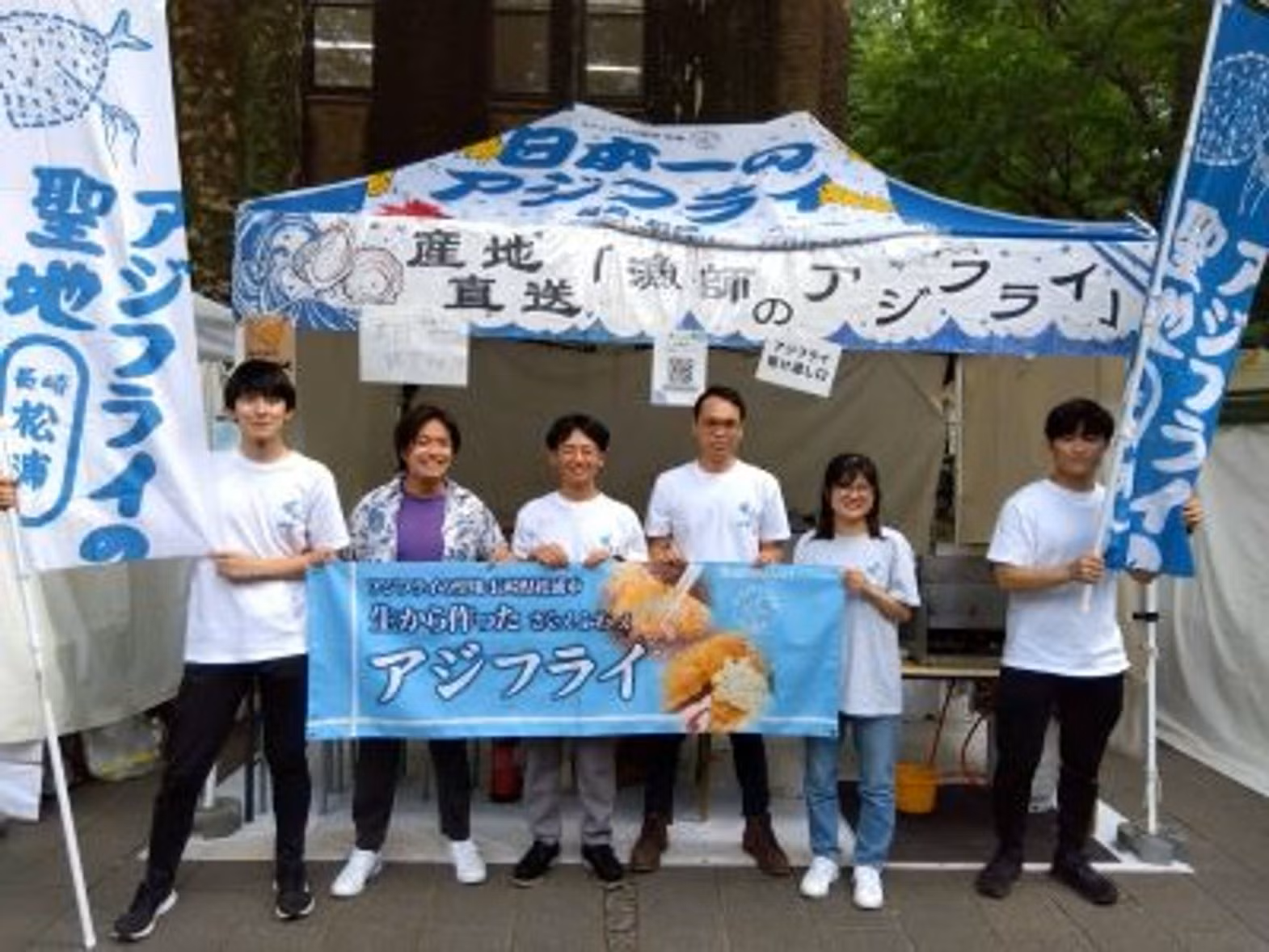







































<未来ビジョン研究センター>
(東京銀杏会・岡田幸村)
<未来ビジョン研究センター>
I love the Earth,
I love the Space(Universe)♡
<未来ビジョン研究センター>