
UTokyo NEXT150(一任する)
総長メッセージ

藤井総長からのメッセージ(2分51秒)
画像をクリックして御覧ください
東京大学は2027年に創立150周年を迎えます。明治10(1877)年に創立された東京大学は、世代を超えて受け継ぎ発展させてきたさまざまな学問の蓄積の上に、社会と広くまた深く関わりながら、この150年の歩みを重ねてまいりました。
2020年代は、新型コロナウイルス感染症や気候変動をはじめ、私たち人類社会の目の前に地球規模の課題が突きつけられており、重要な転換点を迎えている時代といっても過言ではありません。私たちはアカデミアとして、学術が果たすべき役割をしっかりと意識しつつ、何ができるのかを考え、すみやかに行動に移すと同時に、過去から未来にわたる長期的な視野に立って、新しい社会の構築に取り組まねばならないと考えています。
東京大学基金では、この創立150周年を起点に次の150年を目指す未来の歩みを見すえて、新たに“UTokyo NEXT150”と名付けた寄付募集キャンペーンを開始いたしました。東京大学は、これからのたゆまぬ教育研究活動においても、世界に秀でた多様な学知を生み出し、新たな未来を築く卓越した人材を育成し続け、世界の誰もが来たくなる魅力ある大学を創り上げていく所存です。そのためには、国の財政状況や制度の変化に左右されない安定した独自財源を確保することが必要不可欠です。お寄せいただくご寄付は資金面でのご支援にとどまらず、社会のみなさまからの期待として私たちを支え、みなさまとの対話から生まれる力強い後押しとして、本学の経営基盤強化の大きな原動力となるものです。これからの150年を見定めたさまざまな先行投資や、世界の公共性に奉仕する総合大学としての貢献などに有効活用するとともに、大胆で機動的なアクションをも可能にする、東京大学の中核となる基盤的な基金としての拡充を目指したいと考えています。
東京大学がこの先のあるべき未来像をみなさまとの対話を通じて共有し、次の150年を見すえた自律的で創造的な活動を続けていくために、これからも力強いご支援をお寄せくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
東京大学総長 藤井 輝夫
世界の誰もが来たくなるキャンパスを目指して
東京大学は、理念や方向性をめぐる基本方針であるUTokyo COMPASSを2021年9月30日に発表しました。
世界の公共性に奉仕する総合大学として、優れた多様な人材の輩出と、人類が直面するさまざまな地球規模の課題解決に取り組み、また東京大学を「世界の誰もが来たくなるキャンパス」にするために、「知をきわめる」「人をはぐくむ」「場をつくる」の多元的な3つの視点(Perspective)と、これらが好循環を生み出すための自律的で創造的な活動の基盤となる経営力の確立について、具体的な目標と行動計画をまとめたものです。
UTokyo COMPASS「多様性の海へ:対話が創造する未来(Into a Sea of Diversity: Creating the Future through Dialogue)」はこちら
UTokyo NEXT150とは
東京大学は、世界の公共性に奉仕する大学として、その自治と自律を希求すると同時に、社会の要請に応える研究活動を創造することを東京大学憲章において宣言しています。こうした自律的で創造的な教育研究活動を不断に続けながら、その成果を時々刻々と変化する社会ニーズに迅速かつ適切に還元するためには、それを支える独自の財政的基盤を整えることは極めて重要になります。近年のオックスフォード大学の例においても、独自の基金があったからこそ、大学で培われた『知』の成果を、コロナ禍という不測の事態への解決策として、即時に社会実装することができました。
日本で最も長い歴史をもつ大学として、東京大学は、150年に渡って蓄積された広範で多様な知を、いつでも社会に還元できる体制を整えてまいりたいと考えています。創立来の150年に渡る知の蓄積を、次の150年につなげて行きたい。それを実現たらしめる基金を整備したい。そんな思いをこめて、東京大学に一任いただくご寄付に UTokyo NEXT150 という名称を付しました。UTokyo NEXT150 は、平時は東京大学の財政基盤として蓄積され、その運用益とともに、基礎研究を含む本学の自律的で創造的な教育研究活動に充てられます。そして、社会に必要とされる時に、即時利用可能な財源として機能します。みなさまの応援の声を、UTokyo NEXT150 を通じて、よりよい社会に貢献する大学づくりに活かして行きたいと考えています。
大学は 自由意志の“スペース”を作ることによって 社会に貢献できる
我々が直面している新型コロナウイルスの状況で、オックスフォード大学とアストラゼネカという企業が一緒に組み、ひとつのワクチンを開発しています。オックスフォード大学による、非常に大きな、世界に対する貢献だと思います。今年(2022年)の海外出張で2度ほどお会いする機会があったオックスフォード大学のルイーズ・リチャードソン学長からお聞きした話です。
2020年の初めに新型コロナウイルスが出てきて、1月10日に武漢でウイルスの遺伝子情報が公開されました。オックスフォード大学にはもとよりゲノム研究所があり、ワクチン開発研究の優秀なチームがありました。そのチームメンバーが学長のところに来て「新型コロナウイルスのワクチン開発をやりたい!GOサインを出してください」と言いに来たそうです。そして学長は「イエス」と言いました。
彼女は『なぜイエスと言えたのかというと、オックスフォード大学はそれまで数年間積極的に寄付集めをしていて、エンダウメントいわゆる基金として、大学が自由になる資金をしっかり持っていたことが非常に大きかった。』と言うわけです。
『私は過去十数年積極的に寄付集めをしてきたが、なんのためにしてきたのかと言うと、“クリエイティングスペース”つまり、大学の研究者が「これをやるべきだ」「これをやりたい」と言ったときに、それをできるようにするための“スペースを設ける”ということが大事であり、そのために自分は一生懸命寄付集めを頑張ってきた。だから開発チームがワクチン開発をしたいと言ったときに、臨床試験まで考えると相当な資金が必要なのはわかっていたが、私がイエスと言えたのはそのスペースがあったからだ。』
さらにオックスフォード大学が素晴らしいのは、アストラゼネカ社との契約で、「このワクチンを供給するときは利益がでないようにしてください、つまりワクチンをつくるコストのみ、利益を上乗せすることなく、パンデミックの間は“ノンプロフィット(非営利)”にしてください」と約束しました。それは大学が独自で資金を出すことができるから言えたわけです。これがつまりは発展途上国へのワクチン提供にもつながり、30億回分のワクチン供給となりました。
オックスフォード大学のこの出来事は、大学の世界に対する貢献として大変素晴らしいと感じました。こういう風に、大学の人たちがこれをやるべきだと思ったときに、すぐできるようにしておくということは、極めて重要なことだと感じた次第です。
(2022年7月25日 東京大学基金活動報告会 特別鼎談より YouTubeはこちら )
ご寄付の方法
ご希望の金額にて今すぐ支援する方法(1回のご寄付)と、
毎月・半年・年1回にご希望の金額にてずっと支援する方法(継続寄付)があります。
※ 継続寄付について詳しくはこちら
UTokyo NEXT 150(一任する)へのご寄付は、Amazon Payでのお支払いもできます。
150周年記念ロゴつき自動販売機からのご寄付(2024年分)をいただきました
2025年02月10日(月)

2024年2月より設置がスタートした東京大学創立150周年記念事業ロゴマークとメッセージをラッピングした自動販売機は本郷キャンパス周辺から広がり、2024年12月末までに設置台数が10台となっています。
2025年1月にダイドードリンコ株式会社様と自動販売機オーナー皆様より、本自動販売機の売上のうち2024年分として96,240円をUTokyo NEXT150へご寄付いただきました。心より感謝申し上げます。
引き続き東京大学創立150周年を周知・応援いただけますようよろしくお願いいたします。
経済学研究科 特別セミナー『経済理論の社会実装』開催
2023年01月20日(金)

東京大学基金へご寄付をいただいた方々に感謝の気持ちを込めて、特別セミナー「経済理論の社会実装」を、2023年1月20日(金)に開催いたしました。本特別セミナーはオンライン形式で行われました。当日はZOOMウェビナーおよびYouTubeライブにて、最大140名を超える皆様にご視聴いただきました。
特別セミナーの開会にあたり、津田 敦 社会連携本部長よりご挨拶がありました。

前半は「経済理論の社会実装」についてのパネルディスカッションをおこないました。今回は東京大学経済学研究科に附属するセンターの一つである東京大学マーケットデザインセンター(UTMD)における経済理論の研究と、その社会実装に焦点をあててディスカッションを進めました。
ディスカッションを始めるにあたり、経済学研究科長・学部長の星 岳雄 教授より、東京大学経済学研究科と各センターについての簡単な説明がありました。
まずは、UTMD副センタ―長の神取 道宏 教授より、UTMDの概要と研究内容についてお話しいただきました。神取教授はミクロ経済学を専門とされ、特にゲーム理論の分野では世界的な業績をお持ちです。研究対象となる現代社会での具体的な課題を例に、活動の中心の一つである「マッチング制度」の設計と特長についてご説明いただきました。
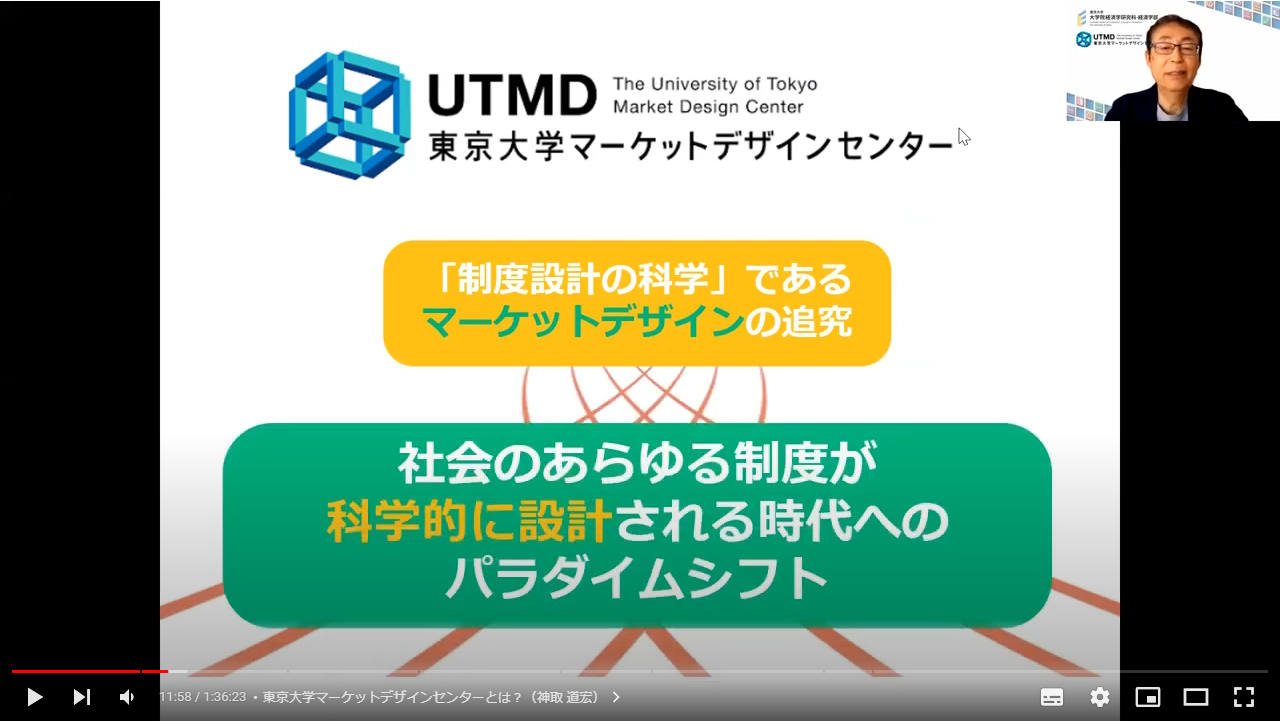
つづいて、小島 武仁 教授より、経済理論の社会実装の実例についてお話しいただきました。小島教授は、主にマーケットデザインを専門とされています。2年前にスタンフォード大学から移籍し、現在はUTMDセンター長を務められています。今回は新規採用者の配属において、希望とのミスマッチが生じることを指す「配属ガチャ」を例に、マッチング制度を導入した具体的な事例をご紹介いただきました。
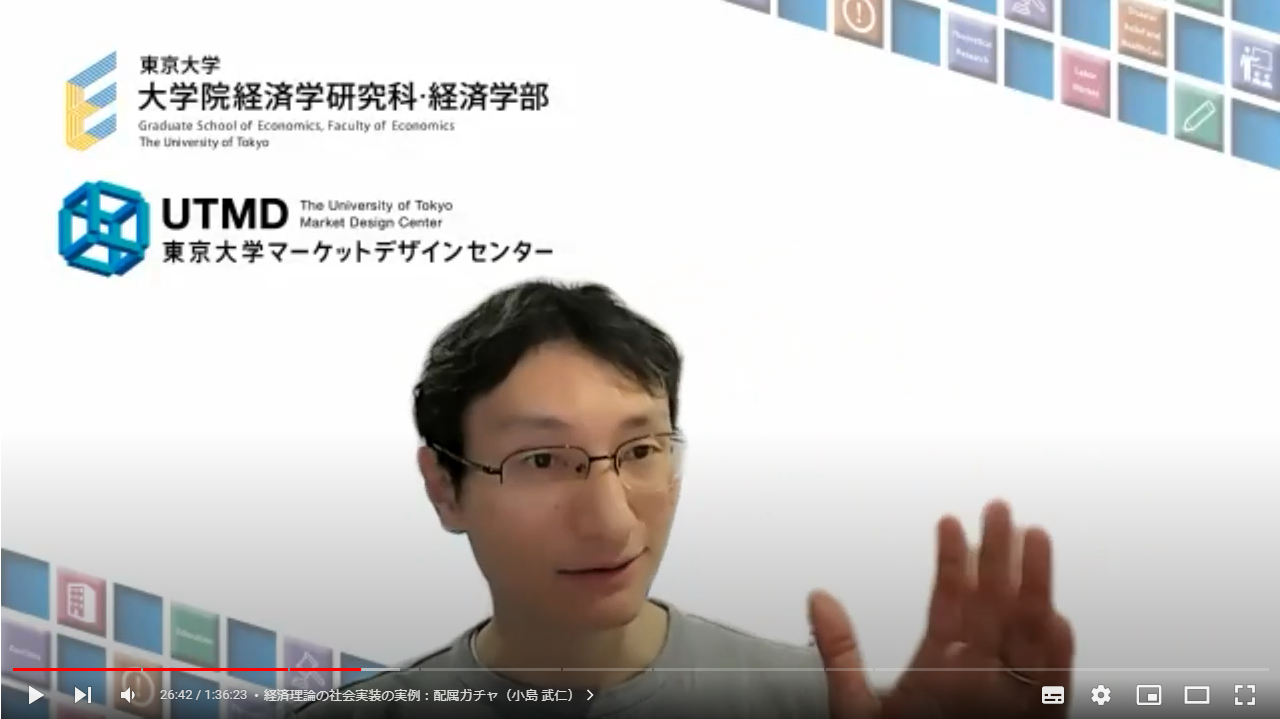
ここで再び神取教授より、制度設計全体の俯瞰図についてお話がありました。今回は特に、現在着目されている「ソフトな制度設計」についてご説明いただきました。「ソフトな制度設計」とは、ルール通りに人々を行動させるのが難しい状況で、人々が自発的にルール通りに動くような環境を設計することを指します。成功事例も踏まえ、今後の展望についても触れていただきました。
最後に、川合 慶 教授より、実践分野である「入札の制度設計と談合」についてお話しいただきました。川合教授は産業組織論を専門とされています。産業組織論は経済学の中でも理論と社会実装の距離が近い分野で、理論・社会実装両方の分野で注目されている教授です。どのような制度設計をすれば談合を防ぐことができるのかという観点から、実際の事例と研究内容の紹介がありました。
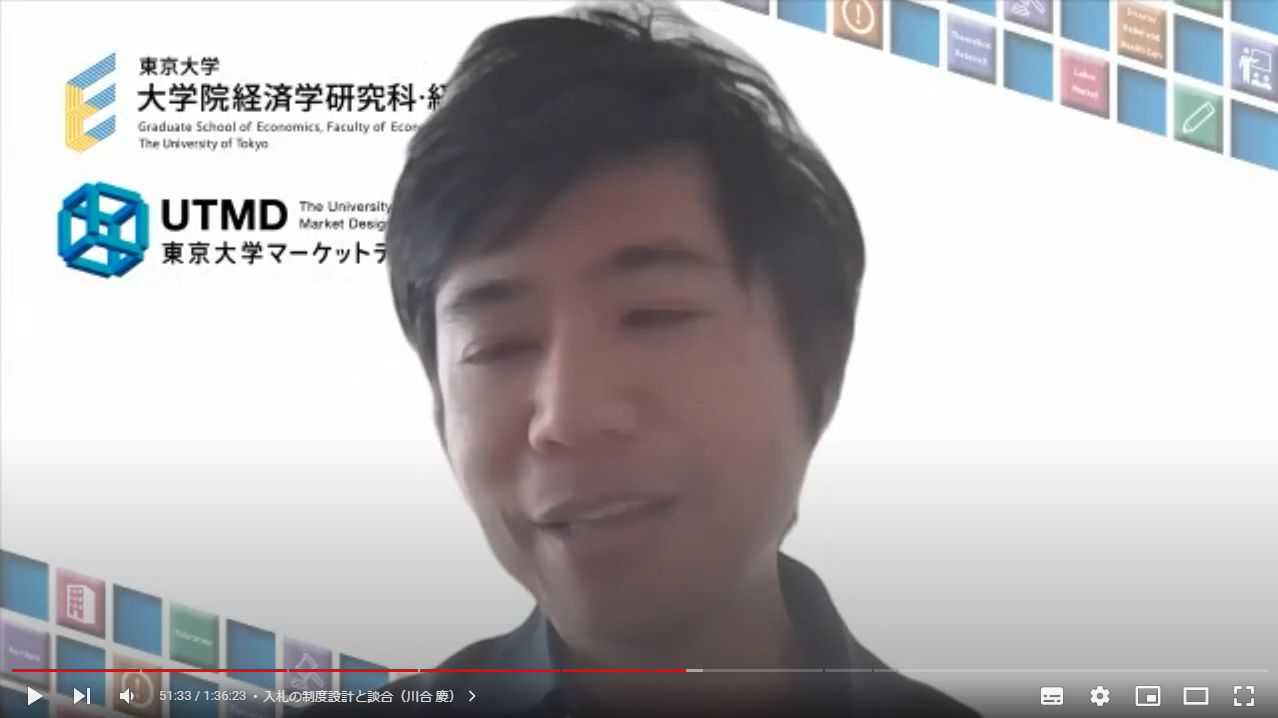
後半は質疑応答の時間がありました。 ご視聴いただいた皆さまよりWEB入力にてご質問・メッセージをいただき、パネリストのみなさまにご回答いただきました。東京大学の進学振り分け制度や就職活動など、身近な分野に関するご質問も多くありました。
また、今後の展望や研究予定について、パネリストの方々からお話がありました。
最後に、星 教授よりご挨拶があり閉会となりました。

東京大学基金は、今後も寄付者の皆様とのご縁を大切にしていきたいと考えております。 引き続き、東京大学基金の活動への更なるご理解、ご支援をよろしくお願いいたします。
人文社会系研究科 特別セミナー『文学部の地域連携活動:これまでとこれから』開催
2021年12月23日(木)
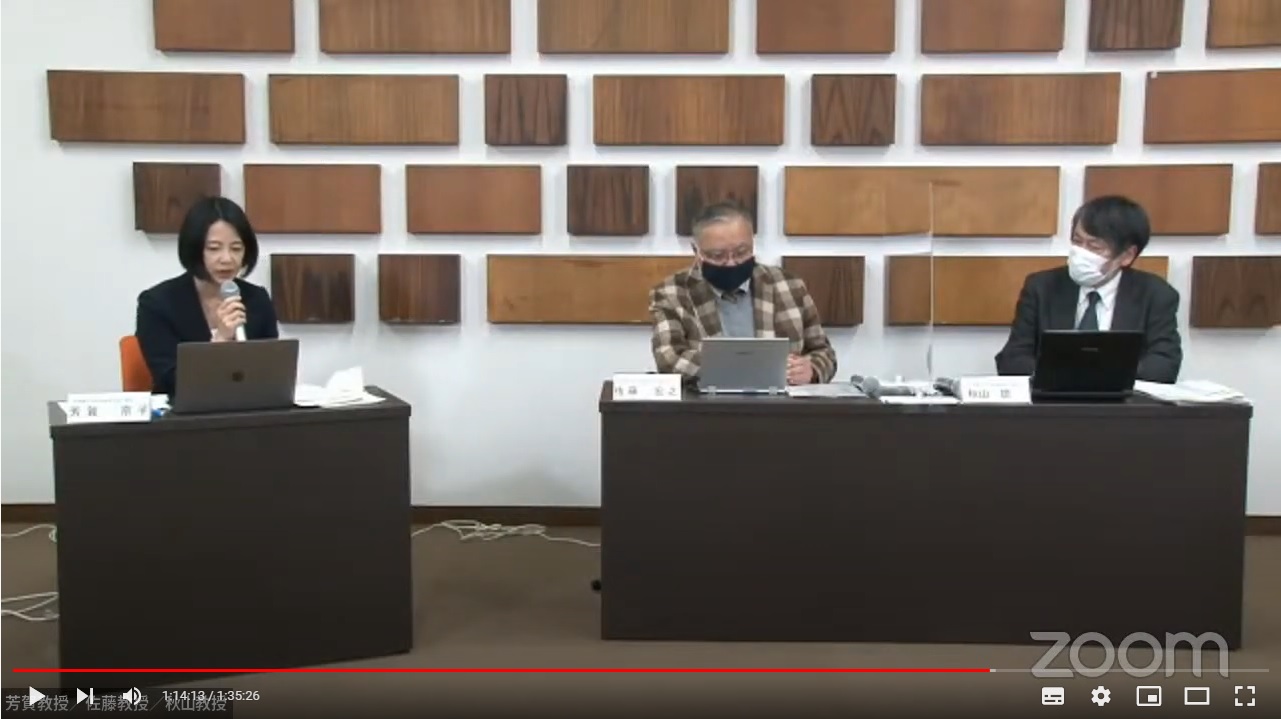
東京大学基金へご寄付をいただいた方々に感謝の気持ちを込めて、特別セミナー「文学部の地域連携活動:これまでとこれから」を、2021年12月16日(木)に開催いたしました。 新型コロナウイルス感染症の流行を考慮し、本特別セミナーはオンライン形式で行われました。当日はZOOMウェビナーおよびYouTubeライブにて、最大80名を超える皆様にご視聴いただきました。
特別セミナーの開会にあたり、研究科長・学部長の秋山 聰教授よりご挨拶があり、文学部及び、これまでの地域連携活動について説明がありました。
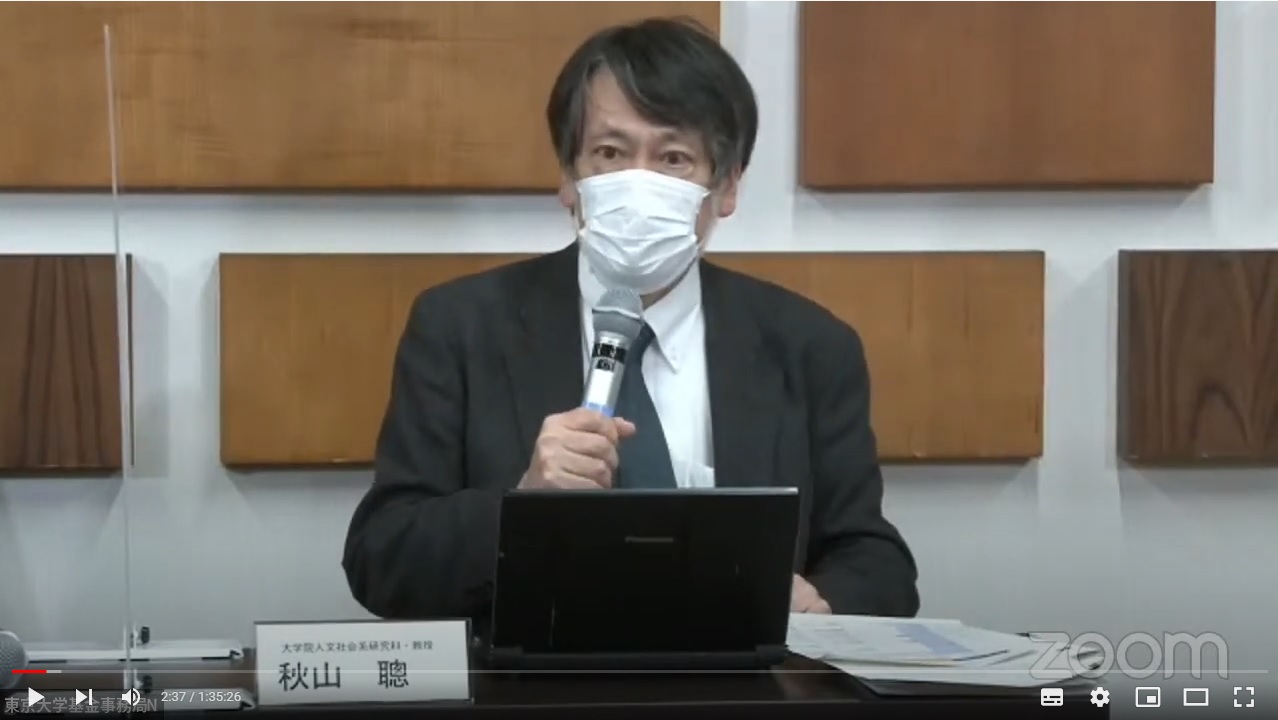
最初の講演は、佐藤 宏之 教授より、「常呂における地域連携の歴史と成果」というタイトルでお話しいただきました。佐藤教授は、先史考古学及び民族考古学を専門とされ、先史考古学としては特に、日本や東アジアの旧石器時代を対象に、民族考古学としては、ロシア極東の先住諸民族と日本列島のまたぎを主に研究されています。今回は、助教授を務めていた北海道北見市の北海文化研究常呂実習施設における地域連携についてお話がありました。文学部と旧常呂町・北見市との地域連携は1957年以来60年以上に及ぶ珍しい例です。
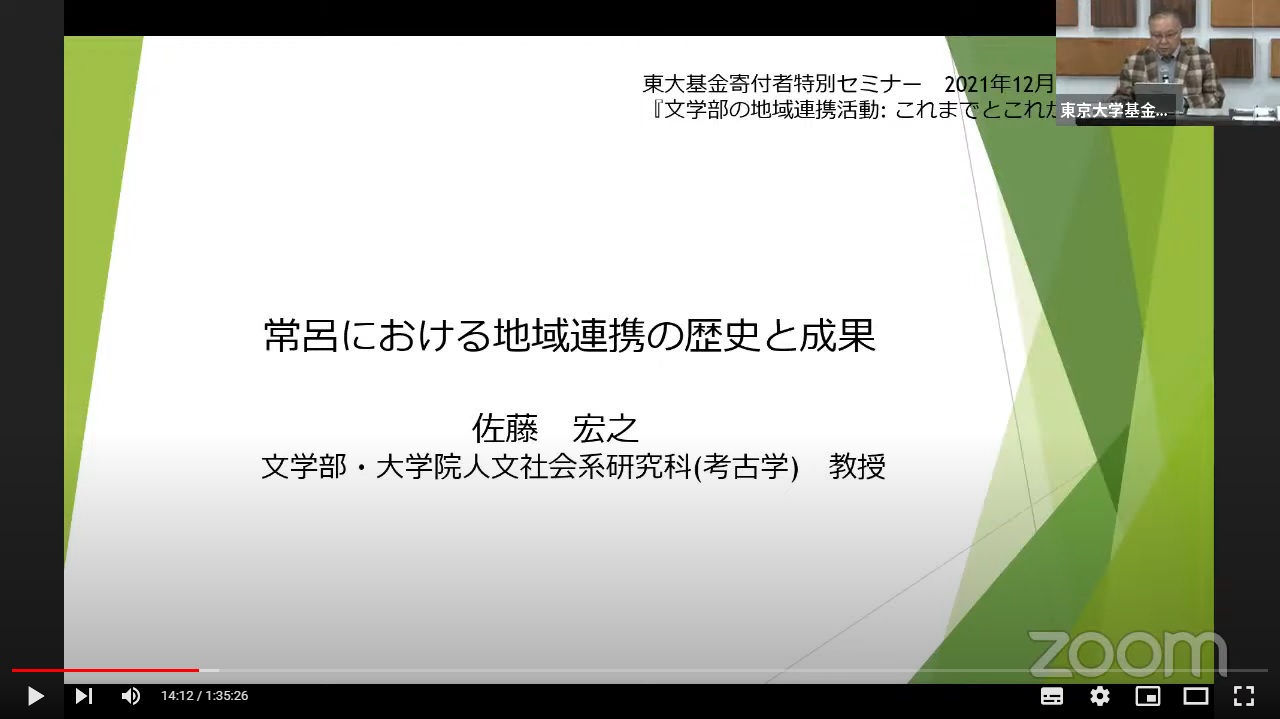
つづいて、秋山 聰 教授より、「東大人文・熊野プロジェクト:地域 連携ネットワーク構築に向けて」と題したご講演がありました。秋山教授は、西洋中世・近世の美術史学を専門とされています。博士の学位を取得されたころには、ドイツのルネッサンス美術の研究をされていましたが、中世宗教美術に興味を移し、その後西洋だけでなく、日本の聖なるものを追い求め、聖地熊野にたどり着いたそうです。今回は、熊野における活動についてお話があり、後半は特に大峯奥駈道の一部を歩いたり、各種体験をした後市民の方に研究発表したりといった東大生向けのプロジェクトについてご紹介がありました。
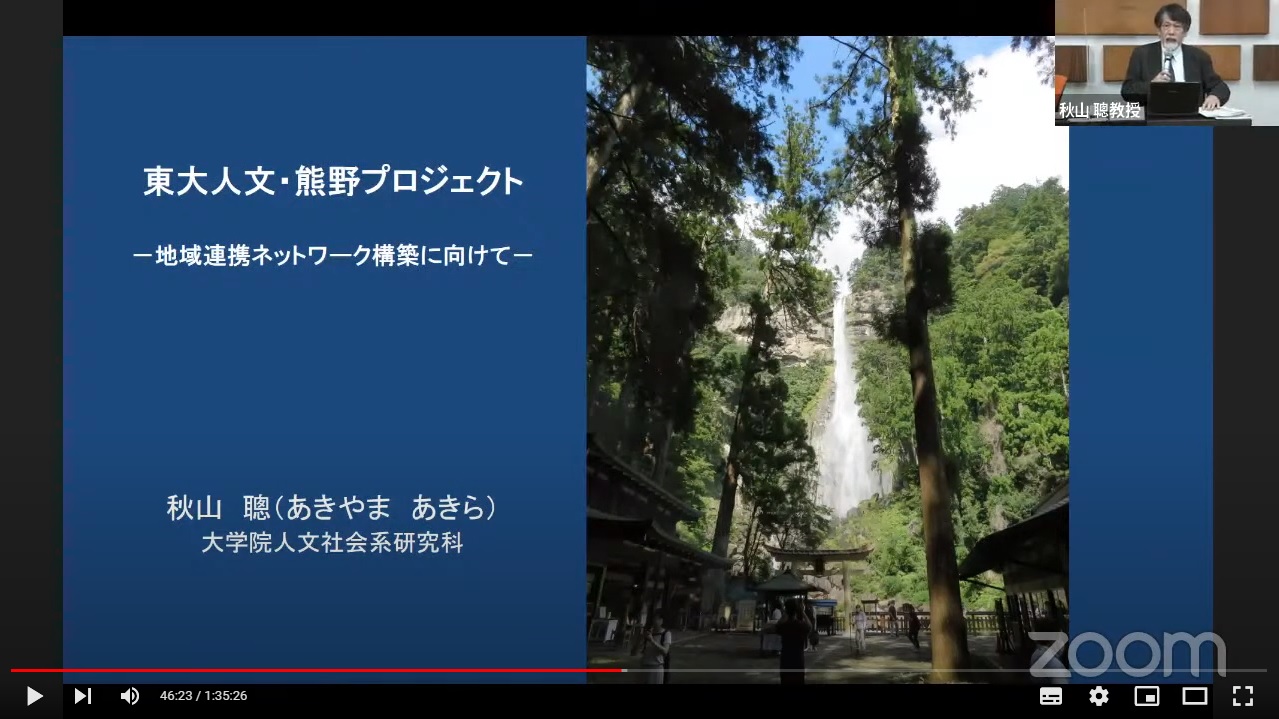
その後、質疑応答の時間がありました。 ご視聴いただいた皆さまよりWEB入力にて多くのご質問・メッセージをいただき、北見市民の方からのご質問や秋山教授が熊野に関心を持った原体験等についてお話がされました。
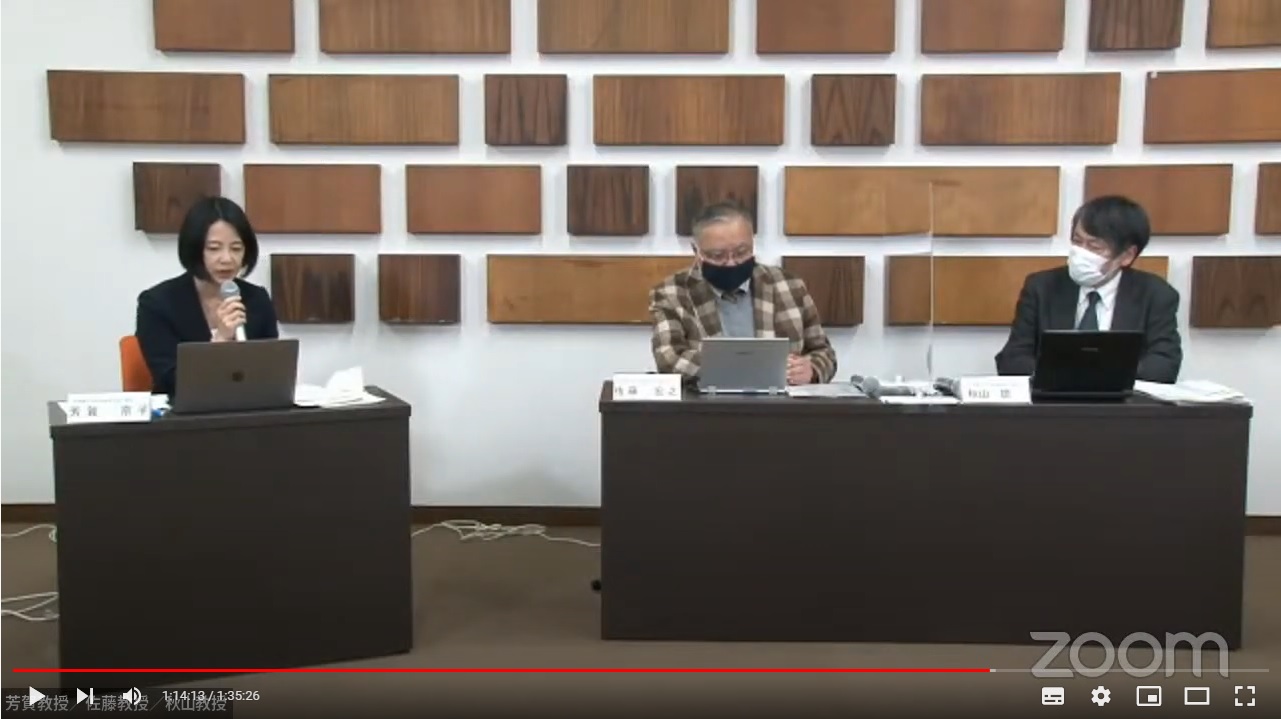
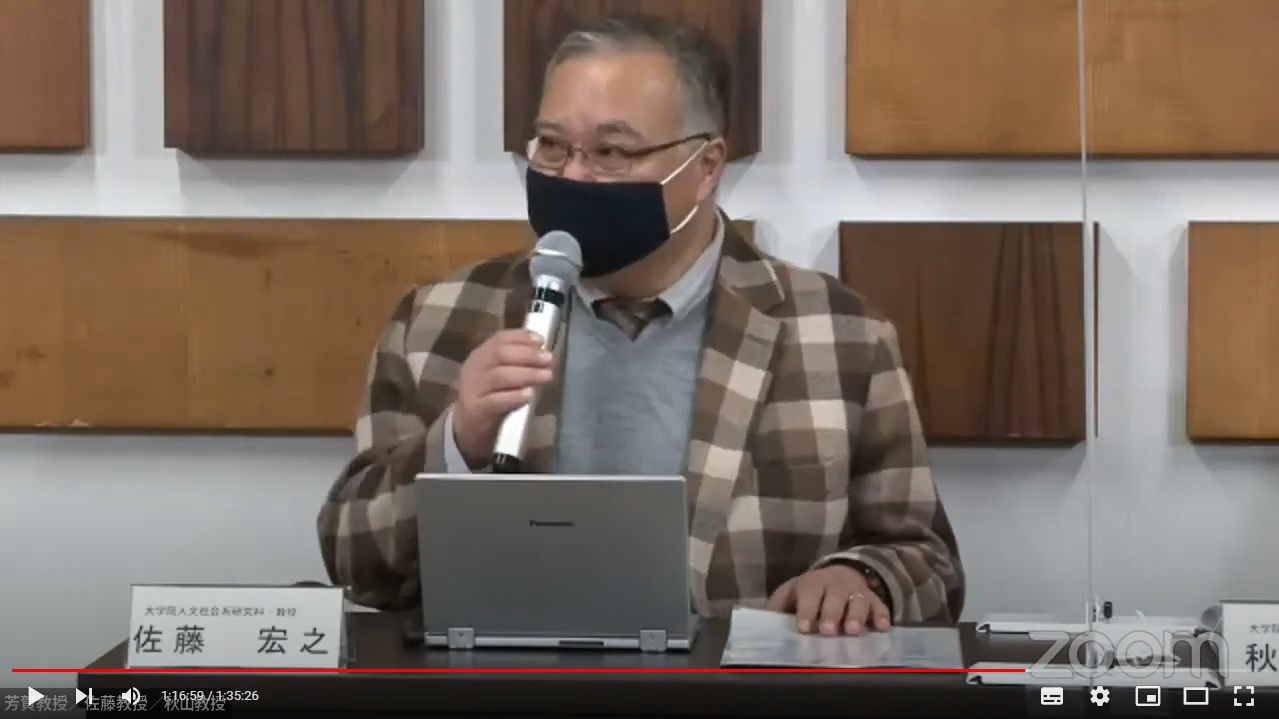
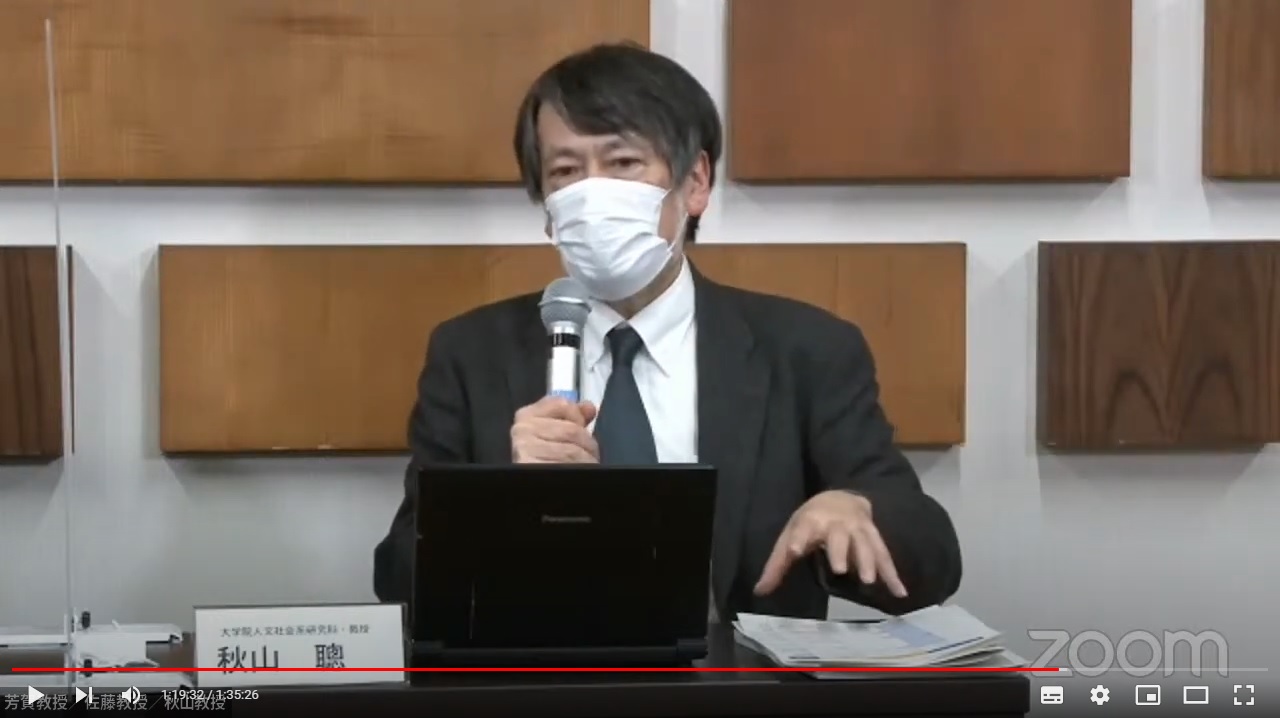
最後に、津田 敦社会連携本部長よりご挨拶があり閉会となりました。
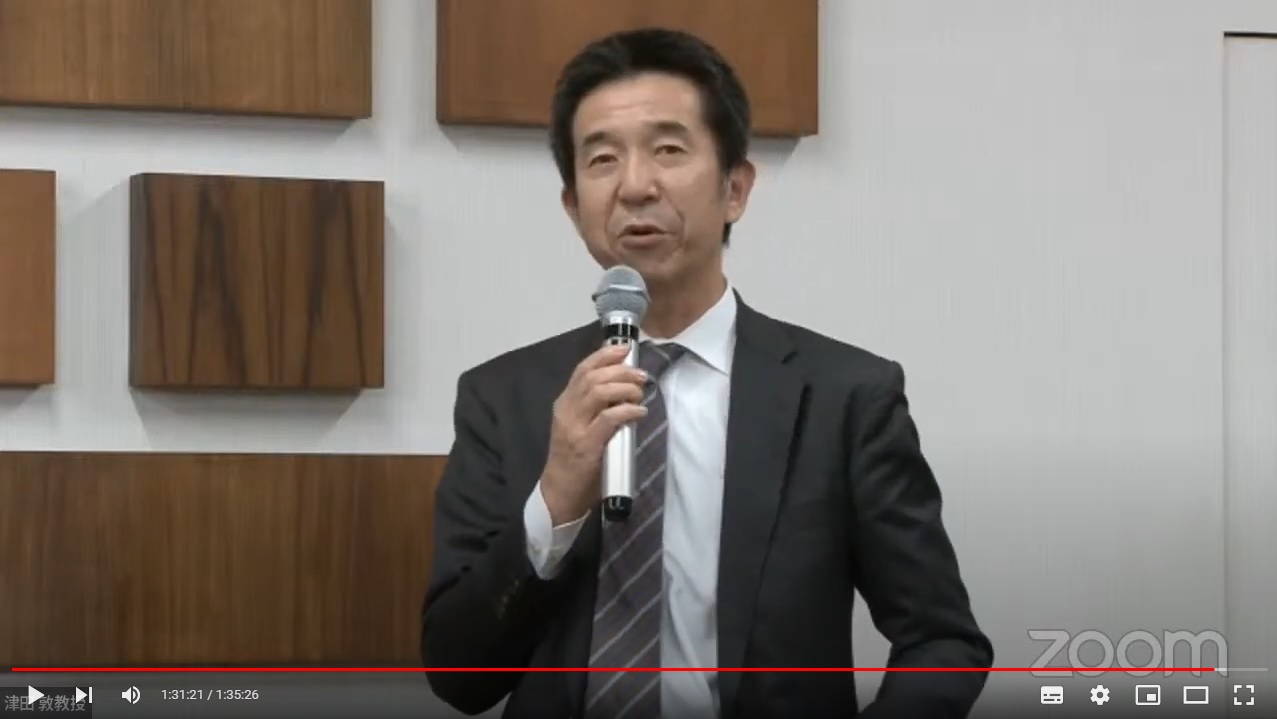
東京大学基金は、今後も寄付者の皆様とのご縁を大切にしていきたいと考えております。 引き続き、東京大学基金の活動への更なるご理解、ご支援をよろしくお願いいたします。
UTokyo Future TV ~東大と世界のミライが見える~ Vol.1アーカイブ動画を公開しています。(ゲスト 藤井輝夫総長×ナビゲーター 渋澤健氏)
2021年12月23日(木)
東京大学基金アドバイザーである渋澤健氏がナビゲーターを務めるオンライン対談「UTokyo Future TV」。毎回多彩なゲストを迎え、様々な切り口で東京大学と世界のミライを紐解く対談をおこないます。
第1回ゲストには、東京大学藤井総長を迎え、就任の抱負や東京大学の新ビジョンについて掘り下げました。
医科学研究所 特別セミナー『「未来医療開発」 ウイズコロナ・ポストコロナ時代の医療に向けて』開催
2020年12月31日(木)

2020年12月15日(火)、医科学研究所 特別セミナー『「未来医療開発」 ウイズコロナ・ポストコロナ時代の医療に向けて』をZOOM ウェビナーおよびYouTubeライブにて開催いたしました。詳細はこちらよりご覧いただけます。
「東京大学基金活動報告会2020」 開催
2020年09月28日(月)
「東京大学基金活動報告会2020」を開催しました。
2019年9月11日(金)、「東京大学基金活動報告会2020」をYouTube配信にて開催いたしました。詳細はこちらよりご覧いただけます。
大気海洋研究所 特別セミナー 『東日本大震災からの再出発-地域の未来に必要な研究所を目指して』開催
2019年11月27日(水)
東京大学基金へご寄付いただいた方に感謝の気持ちを込めて、大気海洋研究所 特別セミナー『東日本大震災からの再出発-地域の未来に必要な研究所を目指して』を11月27日(水)に開催いたしました。
今回は東京大学本郷キャンパスの山上会館大会議室を会場に、『東日本大震災からの再出発-地域の未来に必要な研究所を目指して』と題し、岩手県大槌町にあります大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターの取り組みについてご講演いただきますとのご案内を対象寄付者の方におこなったところ、60名近い応募があり、約40名の方にご出席いただきました。
特別セミナーの開催にあたり、河村知彦 大気海洋研究所所長、および岡部徹 東京大学副学長・社会連携本部副本部長よりご挨拶がありました。
次に、佐藤克文国際沿岸海洋研究センター教授より『バイオロギング天気予報』と題したご講演がありました。佐藤教授は、動物に観測装置を取り付け、人間では観測できない野外環境の生態を調査する「バイオロギング」という研究を続けています。しかし、東日本大震災での経験によってこの「バイオロギング」をこれまで研究を支えてくれた地域の方々への恩返しに使えないだろうか、と考えるようになったそうです。そこで、バイオロギングによる調査によってより正確に海水温を測定することで、海水温に大きく影響を受ける台風進路予測の精度を向上させ、被害を少なくできるのではないかと考え、いま研究に取り組んでいるところだと述べられました。
続いて、河村所長より、『センターの被災~新たな研究活動~再建』と題して、東日本大震災による国際沿岸海洋研究センターの被災状況と、その後のセンターによる未曾有の震災の前後で海の生態系がどう変化したのかに関する、世界的にも類を見ない研究活動の紹介がございました。
講演の間にはコーヒーブレイクがあり、軽食と飲み物を片手に講演者に直接疑問をぶつけられたり、より詳しい話を聴き出されたりする参加者の方が多くいらっしゃいました。
セミナー再開後は青山潤 国際沿岸海洋研究センター教授より、『海と希望の学校 in 三陸、大槌町とセンターの今』と題し、震災後、より地域の未来に必要な研究所を目指すための新たな取り組みとして「海と希望の学校」をご紹介いただきました。
「海と希望の学校」は東京大学の大気海洋研究所と社会科学研究所の共同プロジェクトであり、地域の方々を巻き込んでのローカル・アイデンティティの形成活動を進めるものです。一例として、地域の小中学生を研究所に呼び、様々な体験活動を通して自分の地元の海についての文化や知識を身につけてもらう活動が紹介されました。
全講演終了後は、講演者と参加者の皆さまとの名刺交換交流会がありました。興味深い講演の後ということもあり、参加者の皆さまは名刺交換にとどまらず様々なお話をしてお帰りになりました。
1時間半のセミナーでしたが、あっという間に終了となってしまいました。まだまだ話しを聞きたりない参加者の方もいらっしゃったのではないかと思います。 東京大学基金は、今後も皆さまとのご縁を大事にしていきたいと思っておりますので、引き続き、東京大学基金への更なるご理解、ご支援をよろしくお願いいたします。
「東京大学基金 感謝の集い」(2018年度活動報告会・特別講演会・懇談会)開催
2019年09月04日(水)

「東京大学基金 感謝の集い」(2018年度活動報告会・特別講演会・懇談会)を開催しました。
2019年9月4日(水)、「東京大学基金 感謝の集い」を本郷キャンパスの安田講堂および中央食堂で開催いたしました。詳細はこちらよりご覧いただけます。
生産技術研究所 特別セミナー 『Design-Led X:デザインと工学の融合』開催
2019年06月03日(月)
東京大学基金へご寄付いただいた方に感謝の気持ちを込めて、生産技術研究所 特別セミナー『Design-Led X:デザインと工学の融合』を6月3日(月)に開催いたしました。

駒場リサーチキャンパス(駒場Ⅱキャンパス)にある、生産技術研究所の総合研究実験棟を会場に、『Design-Led X:デザインと工学の融合』と題し、対象寄付者の方に募集を行ったところ、100名以上の応募が有り、約60名の方にご出席いただきました。
冒頭、特別セミナー開催にあたり、岸利治 東京大学生産技術研究所所長及び、岡部徹 東京大学副学長・社会連携副本部長よりご挨拶いたしました。


次に、価値創造デザイン推進基盤を代表し、山中俊治 東京大学生産技術研究所教授より「未来をデザインするために」と題し特別講演がありました。これまでの工業デザインは、出来上がったモノを“カッコよく”すれば消費者に受け入れられるという位置づけで行われるものでしたが、これからのデザインは最新技術や製品仕様ができあがる前から関わることが重要で、それが価値創造デザイン推進基盤の現場で行われているということを、スライドを使用して解説しました。

その後、東京大学生産技術研究所の教授陣によるトークセッション「東大生研が描く価値創造デザイン」が行われました。ファシリテーターとして山中教授が、パネリストとして今井公太郎教授、新野俊樹教授、マイルスペニントン先生が登壇しました。

トークセッションでは、各登壇者が自身の研究を紹介した後、価値創造デザイン推進基盤として進めてきたプロジェクトやその先のビジョンについての討論が行われました。
講演をお聞きになった寄付者の方からは「研究と実践とがこんなにも近くにあると知ることができて大変嬉しかった」との声もありました。
セミナー修了後は、会場を本セミナーパネリストの今井教授が設計した棟へ移し、ご希望される方を「DLX Design Labと生研のプロトタイプ」の展示見学会へご案内しました。見学会では、教授や研究員が直接、寄付者の皆さまに展示物の説明を行いました。皆さま案内を熱心に聞かれており、質問をされる方や、案内終了後も展示をじっくりご覧になる方もいらっしゃいました。「実際に研究の成果物を見られるイベントは貴重でとても魅力的であった」とのお声もいただきました。

特別セミナーから見学会まで2時間にわたるイベントでしたが、ご参加いただいた皆さまにご満足いただけたことをとてもうれしく思います。東京大学基金は、今後も皆さまとのご縁を大事にしていきたいと思います。引き続き、東京大学基金への更なるご理解、ご支援をよろしくお願いいたします。
生産技術研究所Webサイトはこちら
東京大学基金第12回総長主催パーティー
2018/06/27

「東京大学基金 感謝の集い」(2017年度活動報告会・懇談会)を開催しました。
2018年6月27日(水)、第12回目となる「東京大学基金 感謝の集い」が本郷キャンパスの安田講堂および中央食堂で開催されました。詳細はこちらよりご覧いただけます。
東京大学基金第11回総長主催パーティー
2017/06/22
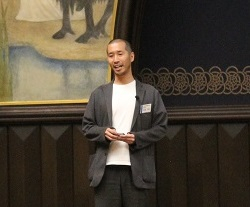
「東京大学基金 感謝の集い」(2016年度活動報告会・総長主催懇談会)を開催しました。
2017年6月22日(木)、第11回目となる「東京大学基金 感謝の集い」が本郷キャンパスの安田講堂および山上会館で開催されました。詳細はこちらよりご覧いただけます。
東京大学基金第10回総長主催パーティー
2016/06/24

「東京大学基金 感謝の集い」(2015年度活動報告会・総長主催懇談会)を開催いたしました。
梅雨半ばとなり、構内の紫陽花も見頃を迎えた2016年6月24日(金)、第10回目となる「東京大学基金 感謝の集い」が本郷キャンパスの安田講堂および山上会館で開催されました。詳細はこちらよりご覧いただけます。
医科学研究所 特別セミナー 『世界一わかりやすいiPS細胞』開催
2015/12/02

東京大学基金へご寄付いただいた方に感謝の気持ちを込めて、医科学研究所 特別セミナー 『世界一わかりやすいiPS細胞』を12月2日(水)に開催いたしました。

今回は、東京大学基金特別セミナーとしては、初めて医療関係のセミナーを実施しました。白金台キャンパスにある、医科学研究所1号館内講堂にて、『世界一わかりやすいiPS細胞』と題し、対象寄附者の方に募集を行ったところ、130名以上の応募が有り、約100名の方にご出席いただきました。当日は、少し肌寒く小雨が降る時間もありましたが、出席者の中には、「講義を是非聴きたくて、会社を休んできました」と言ったお声もいただき、会場内は熱気に包まれていました。
冒頭、特別セミナー開催にあたり、村上善則 医科学研究所長より医科学研究所の紹介があり、次に、大津真 准教授より「iPS細胞の活用~難病と戦う先進医療の今後」について講義がありました。その後、「血液を造る幹細胞とiPS細胞」について、東條有伸 教授の講義が行われ、メモをとる出席者も数多くいらっしゃいました。
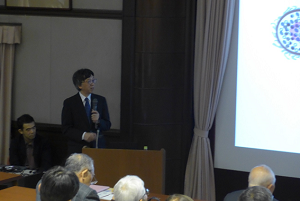
また、特別セミナー後は、医科学研究所内の見学会を開催し、ヒトの生体試料と関連する情報が管理された貯蔵庫「バイオバンク」、医科学研究所の前身である伝染病研究所の初代所長・北里柴三郎博士にまつわる資料など貴重な歴史的資料の数々が展示されている「近代医科学記念館」をご覧いただきました。記念館では、村上所長自ら説明を行い、出席者からは質問が多数寄せられ、意見交換も活発に行われました。

特別セミナーから見学会まで約2時間半にわたるイベントでしたが、ご参加いただいた皆さまにご満足いただけたことをとてもうれしく思います。東京大学基金は、今後も皆さまとのご縁を大事にしていきたいと思います。引き続き、東京大学基金への更なるご理解、ご支援をよろしくお願いいたします。
医科学研究所Webサイトはこちら
東京大学基金第9回総長主催パーティー
2015/06/25

「東京大学基金 感謝の集い」(2014年度活動報告会・総長主催懇談会)を開催いたしました。
梅雨の晴れ間のお天気に恵まれた2015年6月25日(木)、第9回目となる「東京大学基金 感謝の集い」が本郷キャンパスの安田講堂および伊藤国際学術研究センターで開催されました。詳細はこちらよりご覧いただけます。





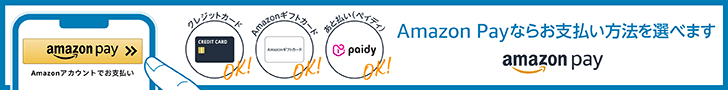
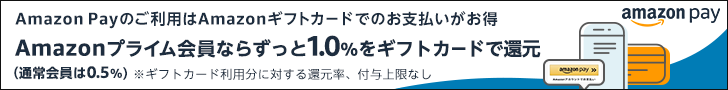


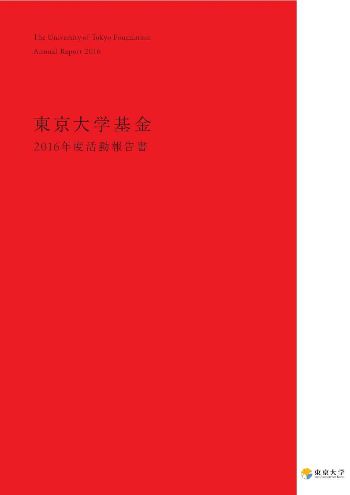






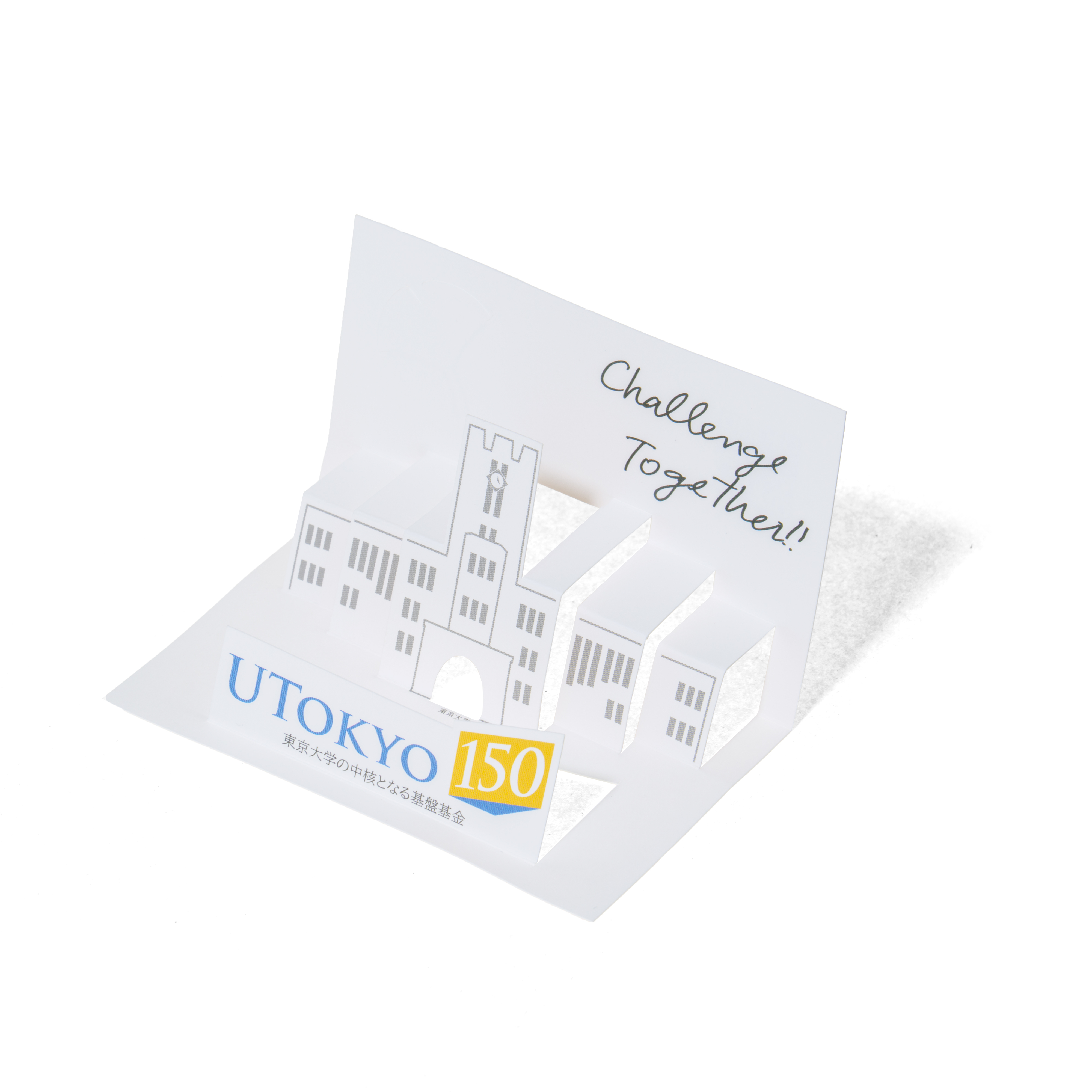

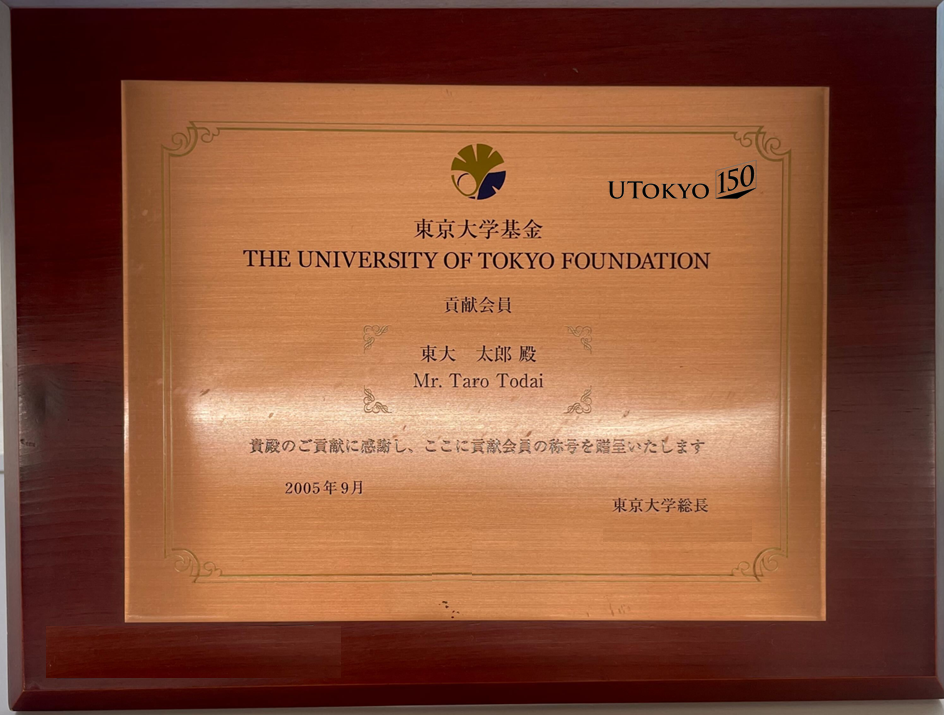




























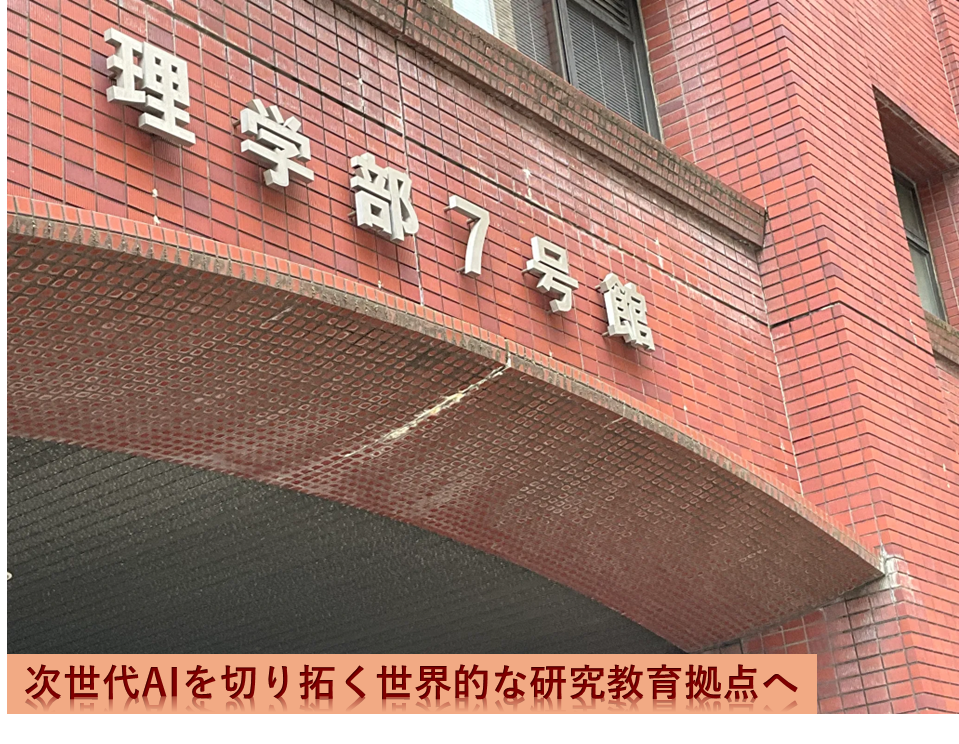










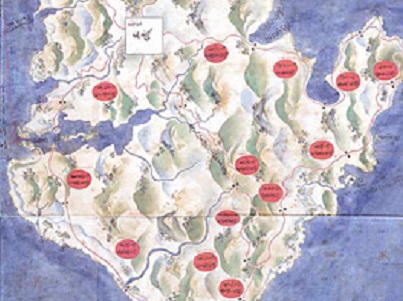





















































<UTokyo NEXT150(一任する)>
卓越大学落選の危機をチャンスに変えろ!J-PIFからガバナンスを奪還し、政治に屈しない知のシェルター構築を。政府に従属するのか、独立した最高学府か、選ぶ時が来た。国民と共に、知の聖域を守り抜け。
<UTokyo NEXT150(一任する)>
<UTokyo NEXT150(一任する)>
<UTokyo NEXT150(一任する)>
スイスのように
日蓮正宗法華講員
<UTokyo NEXT150(一任する)>
<UTokyo NEXT150(一任する)>
<UTokyo NEXT150(一任する)>
あの眩しい輝いている純粋な笑顔、愛、幸せ、豊かさ溢れている
子どもたち、孫たちの笑顔のために
子どもたち孫たちが健康、元気いっぱい毎日伸び伸びと笑顔で過ごせる地域社会、日本、アジア、世界、地球に
<UTokyo NEXT150(一任する)>
<UTokyo NEXT150(一任する)>
<UTokyo NEXT150(一任する)>
<UTokyo NEXT150(一任する)>
<UTokyo NEXT150(一任する)>
<UTokyo NEXT150(一任する)>
<UTokyo NEXT150(一任する)>
<UTokyo NEXT150(一任する)>
<UTokyo NEXT150(一任する)>
<UTokyo NEXT150(一任する)>
<UTokyo NEXT150(一任する)>